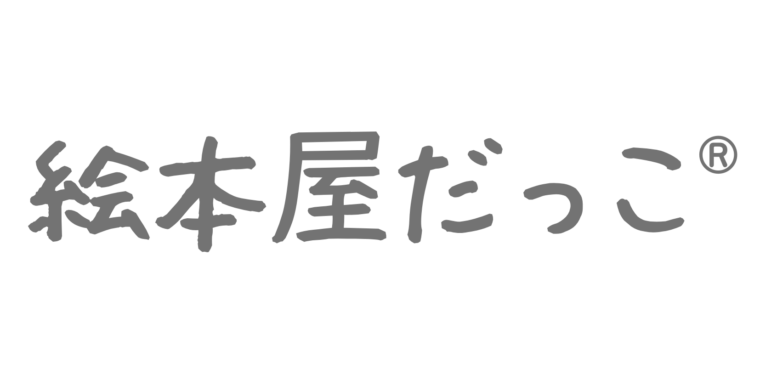こんにちは!絵本屋だっこコラム担当・相談室ピアサポーターのアイスです♪
ちょっとだけ自己紹介します。
【アイスってこんな人!】
- 寝ること・食べることが好きなアラフォー薬剤師
- 2人姉妹を育てており、次女が医療的ケア満載の重心児
- 福祉の支援やケアが必要な子の日常生活について、お母さん同士でおしゃべりしちゃう感覚でコラムを読んでもらえたら嬉しいです。
療育ってなに? はじめての療育ガイド②療育施設の選び方
「うちの子、ちょっと発達がゆっくりかも…」
「周りの子と違うような気がするけど、これって大丈夫?」
「医療的ケアや先天性の疾患があると、発達も変わってくるの?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
わが子が、医師から「リハビリや療育を受けてみませんか?」と提案を受けた日。
最初にその言葉を聞いたときは、正直ピンときませんでした。
「療育って、どうなんだろう?」
「保育園では受け入れ不可とかあるのかな?」
療育という響きがなんとなく特別なことのように感じて、不安もありました。
でも、あのとき一歩踏み出したこと。
今では「やってみてよかった」と思っています。
ここでは、療育の種類と基本的な内容、療育を行う場所選びについてまとめています。

1.療育と保育の違いって?
子どもが日中過ごす場所は、複数あります。
「保育」と「療育」って、言葉は似ているけれど、実はちょっと役割がちがうことを知っていますか?
どちらも子どもを預かってくれる場所ですが、その目的やサポートの内容には違いがあります。
1-1.保育ってなに?
保育園などの保育の場は、家庭での子育てが難しいご家庭をサポートするためのもの。
たとえば、パパやママがお仕事をしている間に、子どもが安心して過ごせるように生活のリズムを整えたり、お友だちと遊んだり、基本的な生活習慣を身につけたりする場所です。
目的は「子どもの生活を支える」こと。
食事やお昼寝、遊びなど、日常生活を通して心と体の成長を見守ります。
また、最近では保育園や幼稚園で加配制度を使って過ごす場合も増えてきているようです。
「加配」とは、障害のある子どもや集団生活を送るにあたって困りごとを抱えている子どもに対し、サポートや援助ができるよう、通常の職員数に加えて先生を配置することを指します。
1-2.療育(児童発達支援)ってなに?
療育は、発達に特性や遅れのあるお子さんが、その子らしく成長できるように支援することです。
言葉がゆっくり、動きが苦手、人とのやりとりが難しい……など、一人ひとりの課題に合わせて専門的なサポートが入ります。
目的は「子どもの発達を支える」こと。
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、看護師、保育士などの専門性が高いスタッフが遊びや活動を通して発達を促します。
療育の種類には、集団タイプと個別タイプがあります。
また、集団か個別かの他にも、親子参加型か親子分離型か、事業所によって違いがあります。
1-3.保育と療育の違いまとめ
・保育とは
- みんなと一緒に育つ場所
- 集団の中で生活を学ぶ場所
・療育とは
- その子に合った育ち方を応援する場所
- その子の発達の段階に合わせて、できることを増やしていく場所
どちらが「正解」かではなく、お子さんの今の状態やご家庭の状況によって、どちらがより合っているかを考えていくことが大切です。
比べるものじゃなくて、必要に応じて使い分ける(療育と保育をあわせて行う施設もあり)ものだと感じています。
2.「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」って何が違うの?
初めての療育に向き合うとき、いろいろな言葉が出てきて戸惑いますよね。
私も、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」など、初耳の言葉ばかりで頭が混乱したのをよく覚えています。
実際に利用してみてわかったことも含めながら、今回はこの2つの違いをわかりやすくまとめてみたいと思います。
2-1.児童発達支援は「未就学児のための療育の場」
児童発達支援は、主に0歳から6歳までの未就学の子どもが対象の通所支援です。
子どもが通っている場所を指す場合もあり、通称「児発(じはつ)」とよばれます。
わが家では、病院の指示に従い、1歳になったタイミングで福祉課を通じて相談支援員さんに繋がり、地域の療育園に通い始めました。
自治体の個別リハビリを受けられる施設もありましたが、集団保育の中での子どもの姿を見たかったため、療育園を選びました。
通っていた園では、言語や運動の個別支援に加えて、集団での遊びや生活動作の練習も行われていて、「遊びながら学ぶ」感覚に近かったです。
何より、親も一緒に成長を見守りながら、スタッフの方と気になることを相談できたのが大きな支えでした。
この時期の療育は、発達の土台を育てるとても大事な時間だと、今振り返って改めて思います。
手術を受けるまでは、わが子は療育園だけに通っていました。
でも、手術後に低酸素脳症を経験し、私たち家族の生活は大きく変わりました。
ちょうどそのころ、地域に放課後等デイサービスを併設した児童発達支援の施設が新しくできました。
「少しでも私が息をつける時間が持てたら…」そんな思いもあって、これまで通っていた療育園に加え、その新しい施設の利用も始めました。
2-2.放課後等デイサービスは「就学後の居場所と成長の場」
小学校に上がると、児童発達支援からバトンを引き継ぐ形で「放課後等デイサービス」が利用できるようになります。
子どもが通っている場所を指す場合もあり、通称「放デイ」とよばれます。
わが家では、重度の医療的ケアがある寝たきりの子どもでも、家や学校までの送迎つきで安全に保育をしてもらえることを第一に考えて、送迎可能な事業所を選びました。
リハビリを兼ねた身体機能のサポートも続けていただいており、家庭だけでは難しいことも一緒にやってくれています。
学校が終わった後や長期休みに通える場所で、みんなで工作をしたり、料理をしたり、ゆっくりとお昼寝をしたりと、まさに「第2の居場所」といった感じです。
親にとっても、放デイの時間はレスパイト(休息)になっていて、「安心して預けられる場所がある」ことのありがたさを日々感じています。
2-3.児発と放デイの違いまとめ
・児童発達支援
対象:0〜6歳の未就学児
利用時間:平日日中(事業所により土日もあり)
目的:発達の土台づくり、就学準備、家族支援
・放課後等デイサービス
対象:小学生〜高校生
利用時間:学校の放課後、休日(長期休みも含む)
目的:自立支援、居場所づくり、社会性の育成
3.療育施設 見学チェックリスト
児童発達支援も放課後等デイサービスも、地域によって内容や雰囲気が異なるため、いざ「どこに通う?」となると迷うことも多いかと思います。
今回は、ここをチェックすれば間違いなし!というポイントをまとめてみました。
初めて見学するご家族でも「どこを見て判断すればいいのか」が整理しやすくなる内容にしています。
児童発達支援・放課後等デイサービス共通で使えますので、ぜひ活用してみてくださいね。
3-1.基本情報の確認
- 施設名・所在地
- 対象年齢
- 定員(1日の受け入れ人数)
- 開所日・時間
- 利用可能な時間帯
- 送迎の有無(自宅・園・学校など、複数の場所への送迎が可能かどうか)
- 医療的ケア対応の可否
3-2.スタッフ体制・専門性
- 保育士・児童指導員が在籍しているか
- リハビリの専門職である作業療法士(OT)・理学療法士(PT)・言語聴覚士(ST)などがいるか
- 看護師が常駐しているか(医療的ケア対応時)
- 子ども一人あたりのスタッフ数(支援の手厚さに繋がります)
- スタッフの子どもへの声かけ・対応は丁寧か
- 保護者への対応(親身で安心感があるか)
3-3.支援内容・活動内容
- 個別療育(マンツーマン支援)の有無
- 集団活動(遊び・リズム・季節の行事など)の充実度
- コミュニケーション支援(視覚支援・AAC等)の有無
- リハビリ(PT・OT・ST)を受けられる体制か
- 学習支援や生活動作の練習内容があるか
- 子どもが楽しそうに活動しているか
3-4.環境・設備面
- 室内が清潔で安全に配慮されているか
- 子どもに合わせた遊具・教材・視覚支援などがあるか
- 医療的ケアに必要な設備(吸引器、酸素、ベッド等)があるか
- トイレやおむつ替えのスペースが整っているか
- 保護者が待機・相談できるスペースがあるか
3-5.その他の確認ポイント
- 契約・利用開始までの流れが明確に説明されたか
- 利用料金(自己負担分)について説明があったか
- 送迎時間・ルートの希望は通りやすいか
- 急な体調不良などへの対応体制があるか
- 緊急連絡の手段・連絡体制は整っているか
3-6. 見学後の印象メモ
- 施設全体の印象は?
- スタッフや子どもの雰囲気は?
- 自分の子に合っていると感じた点・不安に思った点は?
3-7.チェックリストの使い方のアドバイス
- 複数施設を見学する際に、同じチェックリストで比較すると判断がしやすくなります。
- 保護者自身の直感や「安心感」もとても大切です。
- わからない点や不安なことは、遠慮せずに質問しましょう。
「聞いても大丈夫?」と思える雰囲気かどうかも、選ぶ際の大きなポイントになります。
4.施設選びのポイント
希望を全部満たす場所は難しいですが、優先順位をつけて動いていくと案外スッと決まることもあります。
特に重視したいポイントは下記になります。
4-1.支援の方法が子どもにあっているか?
「個別療育が中心か」「集団活動が多いか」など、施設によって力を入れている支援のスタイルが異なります。
子どもの特性・性格・伸ばしたいところなどを総合的に見て判断するのがおすすめです。
4-2.スタッフとの相性・雰囲気
子どもや親が安心して通える雰囲気はとても大切です。
見学の際にスタッフの声かけや表情、他の子どもたちへの対応を見て、「ここなら任せられる」と思えるかが判断の基準になりました。
4-3.送迎や立地、利用時間などの現実的な通いやすさ
医療的ケアが必要な場合は、送迎対応の有無や医療的支援の体制も確認が必要です。
毎日のことなので、無理なく通えるかどうかは親の負担にも関わります。
そして、子どもの様子に合ったところを見つけるには、見学がとても大事です。
複数の施設を見て比べることは決して悪いことではありません。
見学の際には、事前に質問したいことをメモしておくと、見学後の印象も整理しやすくなります。
5.重心児(医療的ケアあり)の子どもの療育
ここでは、わが家が実際に見学や相談を通じて感じた、母子分離の施設選びで大切にしたポイントをいくつかご紹介します。
「重心児のデイサービス(重症心身障害児対象の放課後等デイサービス・児童発達支援)」を選ぶ際には、子どもの安全と成長、そして家族の安心を確保するために、以下のようなポイントを見ることが大切です。
5-1.医療的ケア体制
- 看護師の常駐
何人体制でやっているか?
- 子どもの医療的ケアの対応範囲
吸引、経管栄養、吸入、人工呼吸器管理、胃ろうなど)に対応できるか?
- 医師との連携
かかりつけ医との情報共有、緊急時の対応体制が整っているか?
- 感染対策
重症児は感染リスクが高いため、衛生管理や感染症対策の体制も重要。
5-2. スタッフの質と配置
- 専門職の配置
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などがいるか。
- 人員配置の手厚さ
重心児はマンツーマンや少人数での支援が必要。配置人数は十分か?
- スタッフの経験・姿勢
「重心児に慣れているか」「親との連携を大切にしているか」も確認ポイント。
保育士の子ども(重心児)への関わり方も重要です。
5-3.支援の内容
- リハビリや療育の有無
身体機能の維持・向上やコミュニケーション支援があるか。
- 活動のバリエーション
外出、感覚遊び、季節の行事など、無理のない範囲での活動があるか。
- 子どもに合った個別支援計画
個々の発達や障害特性に合った支援がされているか。
5-4.送迎&通いやすさ
- 送迎の有無・対応範囲
医療的ケアをしながらの送迎が可能か。
- 通える距離か
通所時間が長すぎないか(特に体力のないお子さんは要注意)
5-5.保護者との連携・支援
- 連絡帳や写真での報告
その日の様子や体調を、丁寧にフィードバックしてくれるか。
- 保護者支援
相談に乗ってくれる体制があるか、家族のケアも大事にしてくれるか。
5-6.施設の環境
- バリアフリー設計
ストレッチャーや車椅子、バギー、座位保持装置でも無理なく過ごせるか。
- 衛生面・安全面
医療機器の保管や清掃が適切に行われているか。
- 静養スペース
体調が悪い時に休めるスペースやベッドがあるか。
重心児にとっては、横になってしっかりと休むことができるベッドがあると安心です。
5-7. 体験・見学の対応
- 見学や体験利用ができるか
実際の様子を見て、親子ともにどんな印象を受けるかが重要。
- 説明が丁寧か
基本的な制度やサービス内容、費用などをしっかり説明してくれるかをチェック。
5-8.わが家の重視したポイント
私がいちばん大事にしたのは、「実際に利用した人たちの声」と「これまでの実績」でした。
どんな医療的ケアのある子を受け入れてきたのかを、療育園の先輩ママや地域の相談員さんから事前に聞いてから見学に行きました。
そして、気になることはその場でしっかり質問しました。
実際に通っているママたちの話や子どもたちの様子を聞けると、とても安心できますよね。
それに、もし合わないなと感じたら、施設は途中で変えることもできるんです。
だからこそ、「長く通っている子が多い施設」は、安心できるポイントのひとつになると思います。
6. おわりに
「療育」って、難しそうに聞こえるかもしれません。
でも、実際は子どもに合った方法で、育ちをサポートしてくれるやさしい時間です。
そして、親である私たち自身も支えてもらえる場所です。
1人で頑張らなくても大丈夫。
療育に関する制度や施設はたくさんありますが、「わが子に合う場所」がすぐに見つかるとは限らず、迷いや不安もあると思います。
特に、母子分離の施設の場合、意思表示が難しい子や医療的ケアがある子を1人で送り出すのは、とてもドキドキします。
けれど、どの施設も「子どもの力を信じて支援したい」という思いをもって運営されている場所です。
わが家も、相談と見学を繰り返しながら、その都度「いま必要なこと」に合った施設と出会ってきました。
子どもは強いです。
可能性にあふれています。
保護者のいない環境で過ごすことは、子ども自身の表現を増やします。それが、子どもの自立につながります。

*絵本屋だっこのコラムに関しては、全ての方に当てはまる情報ではございません。
投稿された情報の利用により生じた損害については、絵本屋だっこでは責任を負いかねます。あくまでもご家庭での判断のもと参考情報としてご利用ください。また、特定の施設や商品、サービスの利用を推奨するものではありません。
ひとりで悩んでしまう方は『絵本屋だっこ相談室』へご相談ください


絵本屋だっこでは、障害児ママたちが安心して相談できる場所をつくるため、また、障害児がいて外で働けないママたちの居場所をつくるため、『絵本屋だっこ相談室』を開設しました♪
ぜひお気軽に、ご相談にきてくださいね。
新米ママたちへ向けたお役立ち情報の掲載
こちらのコラムページでは、重心児や自閉症・発達障害などの障害児を育てる先輩ママたちにご協力いただき、新米ママたちへ向けたお役立ち情報を発信していきます!
<コラムに載せる内容例>
- 障害児ママたちの体験談まとめ【連載企画】
- 障害児向けの便利グッズ
- 障害児育児のお役立ち情報
- 障害児が使える福祉サービスについて
- 障害児の将来に関すること など……
今、子どもに障害を宣告され、不安いっぱいのママたち、まだまだ子どもが小さく先が見えず不安なママたちへ、必要な情報を届けられればと思っています。
コラム掲載のご案内は、公式LINEやインスタなどで行なっていきますので、ぜひチェックしにきてくださいね!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
▼絵本屋だっこInstagram


コラム記事を書いてみたい方を募集中!
絵本屋だっこでは、子どもに障害があって外に働きに出られないママたちの働き場所をつくる取り組みをスタートさせました。こちらのコラム記事執筆も、そのひとつです。
報酬は多くは出せませんが、お手伝いいただける方がいればぜひ公式LINEよりお問い合わせください。一緒に活躍の場をつくっていきましょう!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
ボランティアさんも募集中♪
絵本屋だっこコラムでは、障害児ママ以外にも、情報発信をしてくださる方を募集します♪
たとえば、特別支援学校の先生、リハビリの先生、デイのスタッフさんなど、障害児ママたちの不安を解消できるような情報発信をしたいという方がいましたら、ぜひご協力ください!
みなさまのあたたかなご協力をお待ちしております(^^♪