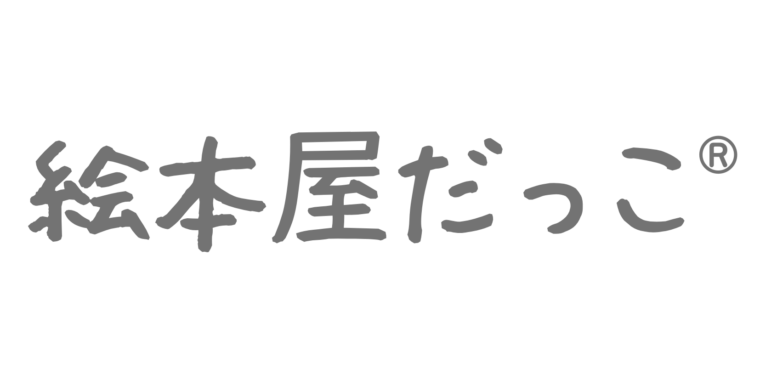こんにちは!絵本屋だっこコラム担当・相談室ピアサポーターのアイスです♪
ちょっとだけ自己紹介します。
【アイスってこんな人!】
- 寝ること・食べることが好きなアラフォー薬剤師
- 2人姉妹を育てており、次女が医療的ケア満載の重心児
- 福祉の支援やケアが必要な子の日常生活について、お母さん同士でおしゃべりしちゃう感覚でコラムを読んでもらえたら嬉しいです。
今回のコラム記事は、連載企画『ママたちの体験談』。
4月からの新生活が始まったみなさんも、少しずつ今の生活に慣れてきたころではないでしょうか?新しい環境で、今まで気にならなかった心配事が出てきた方もいるかと思います。
今回の体験談は、「療育」についてです。
療育(発達支援)とは、簡単にいうと、障害のある子やその可能性のある子について、今後この子をどうやって育てていくのかをみんなで考えていく場所や方法のことです。
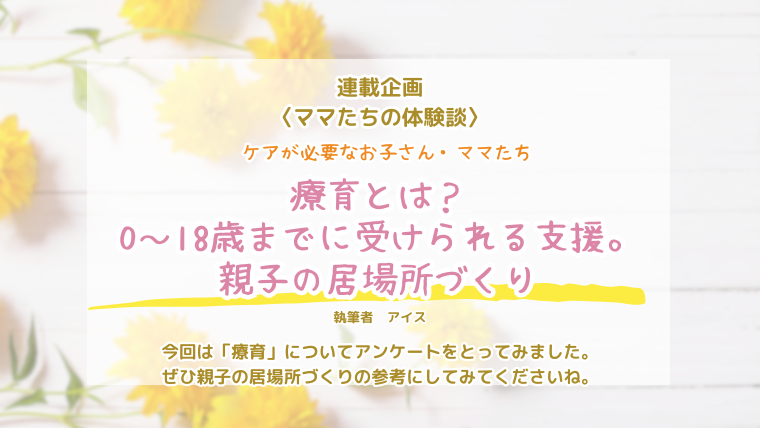
みんなの療育事情~障害児ママたちの体験談~
ここからは、障害児ママたちへのアンケート結果をご紹介します。
ママたちには、以下の質問に回答していただきました。
- 子どもの年齢、性別、特性
医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ(複数選択可能) - 未就学の時に受けたことがある療育の場所や種類
- 小学生以上の時に受けたことがある療育の場所や種類
- 療育を受けるきっかけ&その施設を選んだポイント
- 療育を受けている時に苦痛だったこと
- 療育を受けて良かったこと
ケース1 13歳・重心児ダウン症・男の子の療育事情

かめさんの似顔絵を描いたのは……よしのなおさん♪
似顔絵サービスはこちら>>
①子どもの年齢、性別、特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
13歳、男子、重心。
②未就学の時に受けたことがある療育の場所や種類
- 大学付属病院で、PT
- 市の福祉型児童発達支援通所施設
保育士さんの他に保健師、OT、児童指導員が在籍。在籍途中から相談室開設。 - デイサービス
療育重きの事業所。
日々の活動(SSTやTeacchプログラムを取り入れてる)の他に、
非常勤で資格を持ったビジョントレーニングの先生やOTの先生の指導を受けています。
③小学生以上の時に受けたことがある療育の場所や種類
- 市の発達支援センターで、PT
- デイサービス
(②と同じところ、同じ内容)
④療育を受けるきっかけ&その施設を選んだポイント
- 大学付属病院で、PT
生まれて2ヶ月くらいで、早期療育が必要だと言われました。
生まれた病院の先生が、地域連携先の大学付属病院を紹介してくれました。 - 市の福祉型児童発達支援通所施設
2歳の頃、通っていた大学付属病院のPTの先生から「発達のゆっくりしている息子が通うのにいいよ」と施設を教えてもらい、家族で見学に行き、決定。
福祉型の施設で発達障害の子がたくさんいたため、特性のある子の幼稚園みたいな感じがしました。
保育士さんの他に保健師、OT、児童指導員が在籍。
在籍途中から相談室を開設。
市の施設なので、懇談の他に勉強会などもたくさんあり、親子共にたくさんの事を教えてもらいました。
2歳…親子通園
3歳〜6歳…単独通園
- デイサービス
3歳から居宅介護(入浴介助)で利用していた事業所さんが開設していたデイサービス。
年長さんになったら週1での利用なら可能と言われ、5歳から利用開始。
小学生になる頃には、福祉サービスからは撤退されたが、デイは継続されていたので、週5日(月〜金)と時々土曜日利用中。
- 市の発達支援センターで、PT
大学付属病院のPTが就学と同時に打ち切りに。理由は、自立活動を行なっている学校へ通うからと言われた。
しばらく学校の自立活動のみ受けていたが、
小1の秋頃、学校に診察に来られていた整形の先生から「リハビリをやらなきゃダメだ」とがっつり怒られ、「ボクの行っている所に来なさい」と、市の発達支援センターを紹介されました。
最初は、月2回からのPT→小3で自立歩行が出来るようになったら月1回になり、現在は2ヶ月に1回の頻度で通っている。
小児科と整形の先生が在籍しているので、診察や相談も定期的に受けることができています。
⑤療育を受けている時に苦痛だったこと
市の福祉型児童発達支援通所施設に母子通園していた頃。
母である私が開頭手術後の体調不良がまだまだ大きく、1人で歩けない子を連れて動くのはしんどかったです。
ただ、他のママさん達とたくさんお話出来ましたし、泣きながら保育士さんに相談する事も日常茶飯事な所だったので、しんどい日々の中でも頑張れたんだと思います。
⑥療育を受けて良かったこと
就学前に通っていたところでは、焦りと不安ばかりで実感がわかなかったですが、今振り返ってみれば、子の土台・下地を作ってもらえていたと思います。
現在通っているところは、具体的に出来る事を伸ばしてくださっているので、とてもありがたいです。
子だけでなく親も一緒に、たくさんの知識を吸収させてもらえています。
(NPO法人絵本屋だっこ理事・相談室ピアサポーターかめ)
ケース2 8歳・医ケアあり重心児・女の子の療育事情
 アイスの似顔絵を描いたのは……のだそのえさん♪
アイスの似顔絵を描いたのは……のだそのえさん♪
似顔絵サービスはこちら>>
①子どもの年齢、性別、特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
8歳、女の子、医療的ケアありの重心。
②未就学の時に受けたことがある療育の場所や種類
- 生後半年〜1歳前後
かかりつけの小児科の総合病院での個別療育(主にPTですが、OTの内容も含まれていました) - 1歳〜
療育園(児童発達支援センター)での個別療育(PT)とともに、プレ保育のような形で、5人での集団保育で週1ぐらいの療育を開始。
療育園は、母子通園。 - 3歳前後〜
同じ療育園で引き続き、PT、OT、STの個別療育とともに、
1クラスでの療育を交えた集団保育。
コロナ禍で、数回しか参加できず…
(その後手術が上手くいかず、1年間入院) - 3歳半ごろ〜
リハビリ入院の間、一時的に病院の児童発達支援センターに転院する。 - 低酸素脳症後に医療的ケアありの重心児になってからの4歳〜
在宅移行前に、重心児のデイ(児童発達支援と放課後等デイサービス併設型)を1つ契約し、母のレスパイト目的で通う。
引き続き、以前と同じ療育園に戻り、週1で親子でリハビリやら集団保育やら。
地域に新たに重心児のデイができたので、デイを2ヶ所通うことに。
③小学生以上の時に受けたことがある療育の場所や種類
放課後等デイサービス
②の時からの継続で、2ヶ所通っています。
学校までの送迎もしてくれます。
④療育を受けるきっかけ&その施設を選んだポイント
1番最初は、生後半年ごろの小児科受診で、医師から初めて「療育」という言葉を聞きました。
2回目の心臓手術が終わって体調が落ち着いたころから、療育を開始しました。
1歳前後に、子どものそれぞれの地域に帰すという病院の方針があるらしく、そこで地元の保健師や福祉課経由で相談員さんを紹介してもらい、地元の個別リハビリか隣の市の療育園かと教えてもらい、集団保育が可能な療育園を選びました。
⑤療育を受けている時に苦痛だったこと
療育園は、昔ながらの母子通園の園だったので、親の体調不良時や寝不足時に、車で体ぐにゃぐにゃの子を連れていくのが大変でした。
また、幼稚園の雰囲気で親子でがっつり遊びながらの療育という集団の雰囲気に入っていくのもなかなか疲れる日々でした。
通っていた療育園は、発達障害児向けの施設だったため、通い始めた時には看護師もおらず、肢体不自由児や医療的ケア児の世話は付き添いの母に一任され、動ける子たちと同じ内容の療育をこなすのが心身ともにしんどかったです。
重心児のデイは、送迎付きで1人で楽しんでいってくれたため、特にしんどいことはなかったです。
ただ、最近は以前ほど臨機応変な対応が難しくなっているようで、ケアが少しでも変わると引き継ぎが大変です。
⑥療育を受けて良かったこと
母子通園の療育園では、肢体不自由児はずっとクラスが同じだったので、先輩ママや後輩ママたちと縦の繋がりができたのが、とても心強かったです。
重心児や医療的ケア児の親にしか分からない悩みや愚痴、アドバイスなどをお互い親身になって話ができるので、孤独感が薄れました。
卒業した後も、学校やデイなどの情報交換をしています。
(NPO法人絵本屋だっこ理事・相談室ピアサポーター アイス)
ケース3 8歳と6歳・発達障害・男の子の療育事情

①子どもの年齢、性別、特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
8歳と6歳、両方とも男の子、発達障害。
②未就学の時に受けたことがある療育の場所や種類
地域の療育センターと民間の個別療育の併用。
上の子が年中の時、下の子が2歳の時から始めました。
地域の療育センターは母子通園だったため、上の子は年長の1年のみで、下の子は年中から通い始めました(それまでは、民間の療育施設で2人の時間を別にして療育を受けていました)。
民間の療育施設は、療育センターからの紹介で数ヶ所知りました。
紹介していただいた所に実際に足を運んで見学して決めた感じになります!
③小学生以上の時に受けたことがある療育の場所や種類
上の子は現在小学2年生、放課後デイサービスに行くことを嫌がっているため、どこにも通っていません。
ただ、地域の療育センターとは繋がりがあるため、何かあれば相談できるようになっています。
④療育を受けるきっかけ&その施設を選んだポイント
上の子が3歳の時、役所でやっていた児童発達精神科の医師による相談事業で診てもらったことがきっかけです。
そのまま地域の療育センターを予約→発達検査を受けて、療育へと繋がりました。
下の子は、上の子が療育センターに通園していたことがきっかけで、2歳の時に医師に診てもらいました。そこから、発達検査→診断が下り、療育を受けることになりました。
ただ、地域の療育センターの通園での療育がすぐに受けられなかったのと、早期に療育を受けた方が良いということで、療育センターから紹介してもらった民間の個別療育に行くことになりました。
いくつか候補があり、本人たちが行きたいと言った所に行くことになりました。
ですが、その療育施設が閉所となってしまい、療育センターの枠に空きができたタイミングで、そのまま療育センターで集団療育を受けることになりました。
⑤療育を受けている時に苦痛だったこと
私自身持病があり、その日の体調に波がありました。
そのことで、他のママさんたちに関わることがしんどかったり、通うのに電車を乗り継いで行くことも大変でした。
特に、下の子は暴言や手が出やすいため、他の子に対して強く当たることが多い(現在も療育センターに通園しているため)ことから、そういう瞬間を見る度に本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになったりします。
他のママさんたちは特性だからと気にしてないと言ってくれますが…
⑥療育を受けて良かったこと
我が家は、個別療育と集団療育を受けているので、両方の面からお話させてください。
まず、上の子の個別療育です。
上の子は、体の不器用さが目立ち、粗大運動・微細運動が本当に苦手でした。
そのため、遊びの延長で指先を動かすもの、製作ではさみを使ったものなどを取り入れてくれたり、こちらの要望も聞いてくれた療育を行ってもらいました。
すると、筆圧が弱かった上の子が、少しずつ力の入れ方が分かるようになり、文字を自ら進んで書けるようになりました(以前は、書くのを嫌がっていました)。
他にも、はさみの力の入れ方などもしっかり理解できるようになり、現在は学校でもはさみを使った作業も嫌がることなく、取り組むことができるようになりました。
下の子は、人間関係やコミュニケーションに難しさがあり、現在は集団療育に通っています。
最初のうちは、周りが騒いでいると、暴言を吐いて他の子を威圧することが多かったですが、周りがうるさい時に自分がどうしたら落ち着けるかなどを学びました。
その結果、イヤーマフをつけて、暴言を回避したりできるようになりました。
また、周囲の騒音に辛くなったら、やはり暴言を吐いてしまうことがありました。
そのため、療育の先生や私から「静かにしてって伝えてみて?」と具体的な方法を何度も伝えていくうちに、「今は静かにだよ」と自ら言えるようになりました。
自分の世界に閉じこもっていた下の子は、少しずつ周りの子とも打ち解けあうことができ、今では一緒に自由時間を過ごす友達ができるほど成長しました。
個別療育と集団療育では、いろいろな面で異なったアプローチをします。
その結果、子ども自身ができるようになったことがしっかり増えていくことがわかります。
両方の療育を受けることができて良かったと思っています。
(サポートスタッフ うづき)
ケース4 10歳・医ケアあり・女の子の療育事情

Naoさんの似顔絵を描いたのは……ノアさん♪
似顔絵サービスはこちら>>
①子どもの年齢、性別、特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
10歳、女の子、重心医療的ケアあり。
②未就学の時に受けたことがある療育の場所や種類
◾️入院中:1歳頃〜4歳
- 病院内でのPTによるリハビリ
◾️退院後:4歳〜6歳
- 地域の療育センター
個別PT訓練(月1回)からはじめ、コロナの影響もあり、年長の6月から通園(週2→週3)。
最初の2ヶ月は母子通園だったが、その後は週1のみ母子通園でそれ以外は単独通園。
- 児童発達支援施設1ヶ所
- 日帰り型の短期入所1ヶ所
病院がやっています。
宿泊はできないのですが、日中なら預かってもらえます。
短期入所施設は医師の常駐が必要だそうで、そこが児発や放デイとの違いです。
経営的には短期入所の方が良いみたいです。 - 訪問リハビリ(PT)
③小学生以上の時に受けたことがある療育の場所や種類
- 地域の療育センター
個別PT訓練継続+OT訓練(各月1回ずつ) - 放課後等デイサービス2ヶ所(②の児童発達支援施設と新たにリハビリに強い事業所追加)
- 日帰り型の短期入所1ヶ所(②の事業所)
- 特別支援学校(週5通学)
- 訪問リハビリ(PT)月1回
- 訪問リハビリ(ST:言語と摂食)週1回
④療育を受けるきっかけ&その施設を選んだポイント
入院期間がとても長く、その間に在宅後の環境について調べている中で、近くに住む先輩ママさんと知り合い、地域の情報を教えてもらいました。
その情報を病院のソーシャルワーカーさんに伝え、在宅に移行するタイミングでワーカーさんが各事業所と連絡を取ってくれ、退院前のカンファレンスを皆で集まって実施しました。
そのおかげで、とてもスムーズな在宅への移行となり、療育環境も整いました。
重度の子が通える療育センターはここ1つだけでしたが、バスの送迎があるため、自家用車を持っていなかった当時助かりました。
その他の施設も全て送迎付きです。
児童発達支援(のちに放課後等デイサービス)は、お風呂に入れてもらえることも大変助かっています。
⑤療育を受けている時に苦痛だったこと
入院生活が長く、他の親子よりだいぶ遅く通いだしたので、輪に入れるか、娘もついていけるか不安や心配もありました。
しかし、先生や保護者も皆温かく迎え入れてくれ、特に苦痛を感じたことはありません。
⑥療育を受けて良かったこと
色々な体験、経験を通じて娘の世界が広がったことが一番大きいです。
重い障がいがあっても丁寧に関わること、他者との関わりの大切さを知り、娘の成長を感じられることが喜びにつながっています。
療育センターの通園に通ったことがきっかけで、私自身ももっと学んでみたいと思い、保育士の資格を取得しました。
セラピストなどの専門職の方々とお話しできるのも、とても勉強になります。
子どもにしてあげられることがたくさんある、と気付くと親も前向きな気持ちになれると思います。
また、通園や学校などで親同士の繋がりができたことで、情報交換や悩みや愚痴を言い合えるのも心の支えになっています。
子どもにとっても親にとっても社会と繋がる、人と繋がることがとても大切です。
療育はそのきっかけをたくさん作ってくれる場所だと感じています。
ケース5 25歳・重症心身障害者・女の子の療育事情

①子どもの年齢、性別、特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
25歳、女子、重心(医療的ケアなし)
②未就学の時に受けたことがある療育の場所や種類
- 6カ月〜リハビリ(PT)
- 2歳〜母子療育教室(通園前のプレ保育のような場、1年間だけ通う)
- 3才〜市の療育支援施設、母子通園(週3回)
③小学生以上の時に受けたことがある療育の場所や種類
特別支援学校【小学部】
- PT継続
- 民間の療養マッサージ(のちに放課後デイとなる)
- 民間(当初は特別支援学校の教師による指導)の
静的指間誘導法勉強会へ母子で通う(月1〜2回)
【中学部〜高等部卒業まで】
- PT継続
- 放課後等デイ利用(2カ所)
【学校卒業後】
- 生活介護(デイ)通所(週5)
- 児童施設でのPTは基本18才で終了のため、現在は訪問PTに切り替え(週2)
- 療養マッサージ(訪問/週2)
あん摩マッサージとして保険内で受けています(定期的に医師による同意が必要)
内容は、
マッサージと変形に対する矯正。
(筋萎縮や関節拘縮にたいし改善するよう体を伸ばしていったり)
屈伸や回す運動を取り入れてもらっています。
④療育を受けるきっかけ&その施設を選んだポイント
- PTは、大学病院の定期診察で発達の遅れを指摘された後紹介される。
PTを通じて、親子教室及び通園施設も紹介される。
- 療養マッサージや放課後デイについては、同級生ママさんの紹介で知りました。
⑤療育を受けている時に苦痛だったこと
通園施設へは、母子通園(当時はそこしか選択肢が無し/今は施設が増え母子通園の必要のない施設もあり)だったため、下にきょうだいが生まれてからが大変でした。
はじめはきょうだい児も連れて行き、のちに預かってもらえる保育園を見つけ預けてからの通園をしたりしていました。
また、単純に週2回+週1プールの母子通園が、体力的にキツいときがありました。
そして、お子さんの発達には個性があるので、つい比較してしまったりと辛いこともありました(逆に負担が軽くて申し訳ない気持ちになることもありました)。
私は、もともと集団生活が得意ではなく、皆さんと馴染むのにも苦労しました。
⑥療育を受けて良かったこと
我が子の発達を客観的に見守ってもらえたこと。
ママ同士情報交換できたこと。
通園時に看護師さんに子どもの体調不良のときの状態を見て判断していただけたこと。
→アデノイド/扁桃腺除去術を勧めてもらえたことで、結果としてタイミングよく手術できた。
呼吸と食事と、両方を改善できた。
(同じようなお子さんが先輩で通園時すぐそばにいたのため)
蜜な情報交換が可能で、我が子にとっては最大のメリットとなりました。
★③で受けた「静的弛緩誘導法」★
考案者
元筑波大学附属桐が丘養護学校教諭 立川博(故人)
1981年に、名付けられました。
「静的」…体の関節を動かさないで
「誘導」…子どもが自分で理解し、行うよう導いていくこと。
動作の不自由な子どもたちへの対応方法のなかで、唯一教育の立場から開発されたもの。
障害を、”環境とのやりとりや交わり”がうまくいかなくなる状態と考えている。
私と娘が通ったのは、「親子学習会」というお母さんたちによる自主的な運営で開催されていたものです。学校の先生方も多く学習会に参加してくださっていました(会は全国で90ほどあるそうです)。
場所は、地域のコミュニティセンターを間借りして行っていました。
いつでも、だれにでもできる、
体に触れながら、こころとこころのやりとりも行う方法です。
具体的には、おなかやのどなどのいろんな部位に意識的に触れ、声掛け、働きかける。
子どもがその部位を意識して、
入っていた力を抜いたり、
呼吸が深くなったり、
体のイメージを作って使えるよう導いたりします。
その結果は、
ぎゅっと力が入っている体に触れることで
体がゆるんだり、
腹式呼吸がしやすくなったり、
口やのどの使い方(嚥下や発声など)がよくなったりします(お子さんによります)。
娘の場合。
いちばんわかりやすい変化は、
ぎゅっと握っていた手が開き、使える手(握る/離す)になっていったりしました。
また、てんかん発作で息を詰めがちなとき、
おなかにふれると、少しおなかが上下させられた結果、浅かった呼吸が少し深くできるなどがありました。
【みんなの療育事情-障害児ママたちの体験談】まとめ
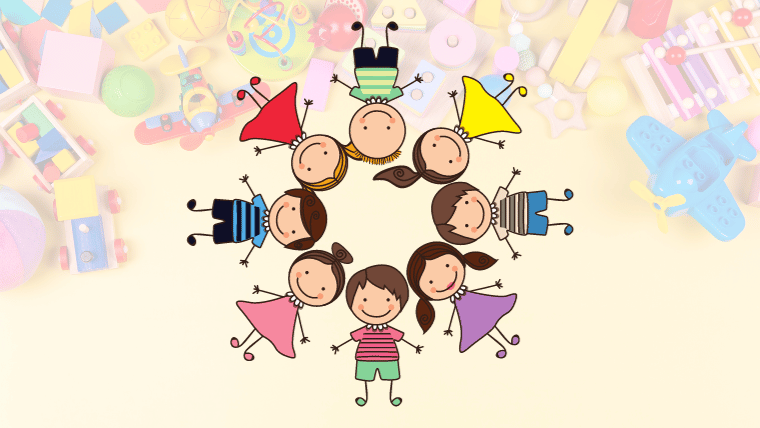
動ける子、動くのが難しい子、医療的ケアがある子、みんなそれぞれのきっかけで療育に通い、つらかったことやうれしかったことを教えてくれました。
体験談を書いてくれたママたちの子供の年齢も障害もさまざまです。
子どもの状態はそれぞれ違っても、ケアの方法についてはお互い参考になるところがあるかと思います。
赤ちゃんから成人した後のケアまで幅広くコラムに書いていますので、ぜひ参考にして下さい。
親子共に少しでも休息する時間が増えますように。
体の疲れが取れて、笑顔で過ごす時間が増えますように。
私は一人じゃないんだ。と感じてもらえたら、私もうれしく思います。
NPO法人絵本屋だっこ理事・相談室ピアサポーター アイス
ひとりで悩んでしまう方は『絵本屋だっこ相談室』へご相談ください

絵本屋だっこでは、障害児ママたちが安心して相談できる場所をつくるため、また、障害児がいて外で働けないママたちの居場所をつくるため、『絵本屋だっこ相談室』を開設しました♪
ぜひお気軽に、ご相談にきてくださいね。
新米ママたちへ向けたお役立ち情報の掲載
こちらのコラムページでは、重心児や自閉症・発達障害などの障害児を育てる先輩ママたちにご協力いただき、新米ママたちへ向けたお役立ち情報を発信していきます!
<コラムに載せる内容例>
- 障害児ママたちの体験談まとめ【連載企画】
- 障害児向けの便利グッズ
- 障害児育児のお役立ち情報
- 障害児が使える福祉サービスについて
- 障害児の将来に関すること など……
今、子どもに障害を宣告され、不安いっぱいのママたち、まだまだ子どもが小さく先が見えず不安なママたちへ、必要な情報を届けられればと思っています。
コラム掲載のご案内は、公式LINEやインスタなどで行なっていきますので、ぜひチェックしにきてくださいね!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
▼絵本屋だっこInstagram

コラム記事を書いてみたい方を募集中!
絵本屋だっこでは、子どもに障害があって外に働きに出られないママたちの働き場所をつくる取り組みをスタートさせました。こちらのコラム記事執筆も、そのひとつです。
報酬は多くは出せませんが、お手伝いいただける方がいればぜひ公式LINEよりお問い合わせください。一緒に活躍の場をつくっていきましょう!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
ボランティアさんも募集中♪
絵本屋だっこコラムでは、障害児ママ以外にも、情報発信をしてくださる方を募集します♪
たとえば、特別支援学校の先生、リハビリの先生、デイのスタッフさんなど、障害児ママたちの不安を解消できるような情報発信をしたいという方がいましたら、ぜひご協力ください!
みなさまのあたたかなご協力をお待ちしております(^^♪