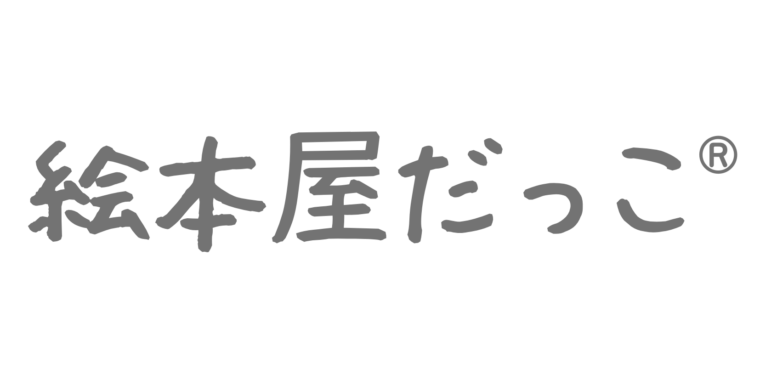こんにちは!絵本屋だっこコラム担当・相談室ピアサポーターのアイスです♪
ちょっとだけ自己紹介します。
【アイスってこんな人!】
- 寝ること・食べることが好きなアラフォー薬剤師
- 2人姉妹を育てており、次女が医療的ケア満載の重心児
- 福祉の支援やケアが必要な子の日常生活について、お母さん同士でおしゃべりしちゃう感覚でコラムを読んでもらえたら嬉しいです。
音で楽しむ、新しい読み聞かせのかたち 〜感性と想像力を育む「おとえほん」〜
絵本の読み聞かせ、しんどいと感じるときありませんか?
「子どもに読み聞かせしてあげたいけれど、疲れて声が出ない」
「きょうだいの世話や家事で手がいっぱい」
「障害がある子どもに読み聞かせをしても反応が薄く、やる気をなくしてしまう」
そんなふうに思ったこと、ありませんか?
絵本は大好きでも、
子どもの知育のためには読み聞かせした方がいいと思っていても、
毎日の読み聞かせがしんどい時って、誰にでもあるはずです。
そんなときに助けてくれるのが、「おとえほん」というCDです。

1.おとえほんとは?耳から楽しむ新しい絵本のカタチ
絵本というと、読み聞かせをしながら、ページをめくって…というイメージがありますよね。
でも、「おとえほん」はちょっとちがいます。
CDや音源がついていて、絵本の物語を「耳で聴いて楽しめる」のです。
お話に音楽や効果音がついているので、まるでラジオドラマや舞台を聴いているような感覚に。
視覚からの情報が入りにくい子や、じっと絵を見るのが難しい子でも、「音」で物語の世界にふれることができるんです。
プロの声優さんや俳優さんの朗読に加えて、場面に合わせた効果音や音楽が流れるので、ただ聴いているだけで物語の世界に入り込めます。
ただの朗読ではなく、映画のようなサウンドで物語が彩られていて、思わず引き込まれてしまうようなエンターテインメントになっています。
1-1.想像力を育てる、やさしい音の世界
おとえほんの特徴は、ストーリーに合わせた音楽が流れる中で語られる、ていねいな朗読です。
目を閉じて聴くだけで、昔話の世界が自然と頭の中に広がります。
視覚に不安があるお子さんや絵を見るのが難しい子にとっても、「音」から物語を楽しめるという大きな魅力があります。
1-2.音へのこだわりがすごい!
音楽は、映画のサウンドトラックを思わせるような、情緒あふれるオーケストラアレンジが物語を包みこみます。
朗読は、やさしく、心に寄り添うような語り口で、聞いているだけで安心感があります。
1-3. 大人にもおすすめ!リラクゼーション効果
実はこの「おとえほん」、大人のリラックスタイムにもぴったり。
全編オリジナルの書き下ろし音楽で構成されており、音楽に身をゆだねるだけで、心がふわっとほぐれていくような感覚があります。
妊娠中の方や、子育てにちょっと疲れたママにもおすすめです。
実際、ご高齢の方にも親しまれていて、年齢を問わず癒しのひとときを届けてくれる作品となっています。
2.想像力を広げてくれる、やさしい時間
おとえほんを聴くと、絵をじっと見られない子や、視覚に不安がある子も、耳から物語を感じとることができます。
「音」でストーリーを想像する体験は、子どもの感性を育むきっかけにもなります。
おやすみ前のひとときや、車でのおでかけ中など、自然に楽しめるのも魅力です。
そして何より、障害の有無に関わらず、どんな子どもにもおすすめできるのが「おとえほん」。
耳から楽しむ時間は、すべての子にとって特別な体験になります。
3.ママ自身のリラックスにも
実は「おとえほん」、子どもだけじゃなく大人にとっても癒しの存在です。
オーケストラのような音楽に身をゆだねれば、忙しい毎日の中でちょっと肩の力が抜けるはずです。
「今日は読む元気がないな」という日も、CDをかけて子どもと一緒に聴くだけでOK。
「読んであげられなかった…」
「何も遊んであげられないまま、今日一日がいつの間にか終わってしまった…」
という罪悪感もなくなりますよ。
4.こんな子におすすめ!
- 視覚に不安がある子
- 絵をじっと見るのが苦手な子
- 音に興味を示しやすい子
- ママの手が離せないときにも、ちょっとしたお楽しみ時間に
5.音のちからを信じて ― ICUでの読み聞かせ体験
「脳のダメージが激しいため、視覚や聴覚がどのくらい残っているのか分からない」
娘の低酸素脳症が分かったとき、医師からそう説明を受けました。
でも、医学的には「人間の聴覚は最後まで残る」と言われています。
それなら、少しでも脳への刺激になればと、手術前から好きだった絵本を読み聞かせ始めました。
ICUはとても静かな環境だったので、医療スタッフにお願いして常に音が届くように工夫していただき、私がいないときにもお話が聞けるように調べて出会ったのが「おとえほん」でした。
最初はずっと眠っていた娘。
CDの声が本当に届いているのか分かりませんでしたが、ヒーリングミュージックやおとえほんを流していると、酸素濃度や心拍が安定することが増えていきました。
「音のリズムや声の抑揚が、やさしく心に届いているのかな」と感じた瞬間です。
さらに、昔読んだ日本昔話やアンデルセン童話が流れると、うっすらと微笑むこともありました。
一年の入院を経て在宅に移行し、4年目の今。
娘は声かけによく反応し、絵本を目で追ったり、読み聞かせに合わせてもぐもぐと口を動かしてお話をするような仕草を見せてくれるようになりました(気管切開をしているので声は出ませんが、ときどき発音もあります)。
振り返ると、聴覚を通した刺激が娘の成長を支えてくれたのだと思います。
音や声は、見えなくても、動けなくても、心に届く。
そう実感しています。
6.同じように悩むママへ
「聞こえているのかな?」
「意味があるのかな?」
と不安になることもあるかもしれません。
でも、たとえ反応がなくても、声や音は必ず子どもの心に届いていると私は信じています。
読み聞かせや音楽は、ママ自身の安心にもつながります。
完璧でなくても、大丈夫。
日々の中で、少しでも親子にとって心地よい「音の時間」を持てたら、それだけで十分だと思います。
7.おすすめの楽しみ方
わが家では、
・おやすみ前に
ベッドの灯りを消して、耳から物語を。
元気いっぱいに動き回り、興奮でなかなか寝つけない上の子の入眠儀式として、幼稚園時代から小学生になる現在まで大活躍しています。
・車の中で
移動時間も退屈せず、落ち着いて過ごせます。
・ママの休憩時間に
子どもと一緒に聴きながら、ママもコーヒーでひと息ついたり。
一緒に横になってごろごろしたり、うとうとしたりするのもおすすめです。
8.おわりに
絵本の読み聞かせがしんどい時、無理をしなくても大丈夫。
「おとえほん」があれば、親子で一緒に楽しみながら、心地よい時間を過ごせます。
障害の有無に関わらず、子どもも大人も楽しめる「耳からの絵本体験」。
新しい読み聞かせのスタイルとして、ぜひ取り入れてみてくださいね。
そして、いちばん伝えたいのは
「どうか一人でがんばりすぎないで」ということです。
悩んだり迷ったりするのは、あなただけじゃありません。
お子さんやご家族にとって、今いちばん大事なことは何か。どんな制度やサポートがあるのか。そして、これから成長していく中でどんなことが出てくるのか。
そんなヒントが見つかるかもしれない「絵本屋だっこ」の体験談を、ぜひ読んでみてくださいね。
コラムでは、乳幼児から成人した子どもとの暮らしについて、ママたちが回答しています。
親子ともに、心身ともに無理ない暮らしを長く続けていく方法をみんなで考えていきたいですね♪
*絵本屋だっこのコラムに関しては、全ての方に当てはまる情報ではございません。
投稿された情報の利用により生じた損害については、絵本屋だっこでは責任を負いかねます。あくまでもご家庭での判断のもと参考情報としてご利用ください。また、特定の施設や商品、サービスの利用を推奨するものではありません。
ひとりで悩んでしまう方は『絵本屋だっこ相談室』へご相談ください

絵本屋だっこでは、障害児ママたちが安心して相談できる場所をつくるため、また、障害児がいて外で働けないママたちの居場所をつくるため、『絵本屋だっこ相談室』を開設しました♪
ぜひお気軽に、ご相談にきてくださいね。
新米ママたちへ向けたお役立ち情報の掲載
こちらのコラムページでは、重心児や自閉症・発達障害などの障害児を育てる先輩ママたちにご協力いただき、新米ママたちへ向けたお役立ち情報を発信していきます!
<コラムに載せる内容例>
- 障害児ママたちの体験談まとめ【連載企画】
- 障害児向けの便利グッズ
- 障害児育児のお役立ち情報
- 障害児が使える福祉サービスについて
- 障害児の将来に関すること など……
今、子どもに障害を宣告され、不安いっぱいのママたち、まだまだ子どもが小さく先が見えず不安なママたちへ、必要な情報を届けられればと思っています。
コラム掲載のご案内は、公式LINEやインスタなどで行なっていきますので、ぜひチェックしにきてくださいね!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
▼絵本屋だっこInstagram

コラム記事を書いてみたい方を募集中!
絵本屋だっこでは、子どもに障害があって外に働きに出られないママたちの働き場所をつくる取り組みをスタートさせました。こちらのコラム記事執筆も、そのひとつです。
報酬は多くは出せませんが、お手伝いいただける方がいればぜひ公式LINEよりお問い合わせください。一緒に活躍の場をつくっていきましょう!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
ボランティアさんも募集中♪
絵本屋だっこコラムでは、障害児ママ以外にも、情報発信をしてくださる方を募集します♪
たとえば、特別支援学校の先生、リハビリの先生、デイのスタッフさんなど、障害児ママたちの不安を解消できるような情報発信をしたいという方がいましたら、ぜひご協力ください!
みなさまのあたたかなご協力をお待ちしております(^^♪