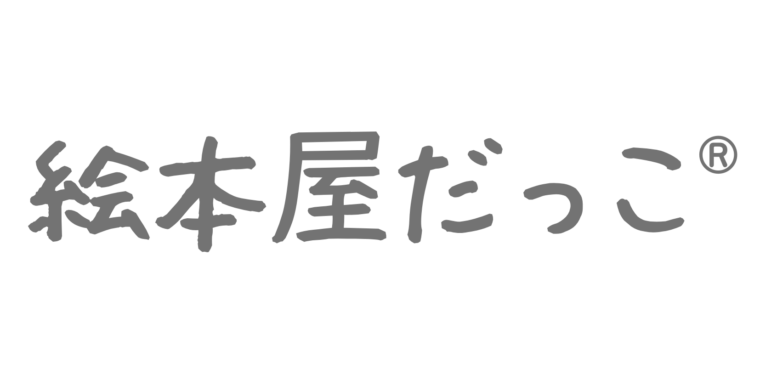こんにちは!絵本屋だっこコラム担当・相談室ピアサポーターのアイスです♪
ちょっとだけ自己紹介します。
【アイスってこんな人!】
- 寝ること・食べることが好きなアラフォー薬剤師
- 2人姉妹を育てており、次女が医療的ケア満載の重心児
- 福祉の支援やケアが必要な子の日常生活について、お母さん同士でおしゃべりしちゃう感覚でコラムを読んでもらえたら嬉しいです。
デフリンピック開催に寄せて|「見えにくい障害」と補聴器ユーザーをもっと知ってほしい
2025年11月15日に、デフリンピックが開催されました。みなさん、デフリンピックって、ご存知でしょうか?
デフリンピックとは、聴覚に障害のあるアスリートを対象とした、国際的な総合スポーツ大会のこと。オリンピックと同様に4年に一度、夏季・冬季大会が開催され、視覚的なスタート合図(フラッシュランプなど)や、旗を使った反則の通知など、聴覚に障害のある選手が公平に競技に参加できるよう工夫されています。

1. はじめに
デフリンピックのニュースが流れるたびに、「聞こえないのに、安全にスポーツってできるんだ?」と不思議に思いませんか?
それと同時に、こんなことも思うんです。
「聴覚障害って、外から見えにくい」
補聴器をしていても、ぱっと見では分かりません。
聴覚を活用できる状態だと、状況によっては呼びかけに反応できることがあります。
しかし、呼ばれていることにそもそも気づかないこともあります。
そのため、周りの人から「無視しているの?」など誤解されることも。
今回のデフリンピック開催は、私にとって 「聴こえにくさ」を知ってもらうきっかけが増えるチャンス。
補聴器ユーザーとしての私自身のことも交えながら、少しお話しさせてくださいね。
2. 難聴ってどんな状態?
聞こえにくさとは、客観的な評価がとても難しいもの。
視力とは違い、「難聴」とひとことでいっても聞こえ方は本当にさまざまです。
- 音は届くけれど、言葉として聞き取りにくい。
- 静かな場所はまだいいけれど、雑音があると一気に何を言っているのか分からなくなる。
- 相手の表情や口元に頼って、言葉を推測しながら会話しているため、疲れやすい。
こんなふうに、「音としては認識できているのに、言葉の聞き取りができない」という独特の困りごとがあります。
具体的には、
水中で話しかけられているような…
遠くのラジオをがんばって聞いているような…
といった表現をする人もいます。
しかし、実際にその人がどのように聴こえているのかは、個人差がとても大きいのです。
2-1.難聴の種類
難聴には、主に3種類あります。
・伝音難聴(外耳、中耳)
外耳や内耳に原因があり、音が伝わりにくい難聴です。
逆に言えば、音が十分に伝わりさえすれば、内耳や聴神経に問題は無いため、言葉は聞き取りやすいです。
大きな声での対応が有効なケースです。
・感音難聴(内耳、神経など)
「音を感じ取る(分析する)」のが難しい難聴です。
振動としての音の伝わりには問題がないが、音のゴールである内耳、神経、脳になんらかの原因があるため、音を聞く・言葉を聞き取ることが難しいです。
例えば、「しちじ(7時)」と「いちじ(1時)」を聞き間違うように、音が歪んで聞こえるため、大きな声でも音の聞き取りが難しいことが多いです。
・混合難聴
感音難聴と伝音難聴の両方が合併している難聴。
2-2.難聴の程度
普通の聴力検査では、どれくらいの大きさの音が聞こえるか検査をします。
その検査結果によって聴力レベルを推測します。
ただ、実際の生活では、どれくらい言葉を聞き取れるかも重要になります。
そのため、言葉をどれくらい正確に聞き取れるかを検査する「語音明瞭度検査(語音聴力検査)」というものもあります。
- 正常(0〜25dB)
- 軽度難聴(25〜40dB)
小さな音や騒音下での会話は困難。
会議などでの聞き取りが難しいこともある。
- 中等度難聴(40〜70dB)
普通の大きさの声での会話が困難。
- 高度難聴(70〜90dB)
非常に大きい声が補聴器がないと聞こえない。
たとえ聞こえていても、会話の聞き取りには限界があると言われている。
- 重度難聴(90dB〜)
補聴器でも聞き取れないことが多い。
人工内耳を考慮する。
2-3.難聴の原因
難聴の原因には、先天性のものと後天性のものがあります。
そして、実は原因がはっきりわからないことも多いんです。
・先天性難聴の主な原因
遺伝性難聴、子宮内感染(サイトメガロウイルス、風疹など)、出生時の状態(低酸素、重度の黄疸、低出生体重児など)
・後天性難聴の主な原因
慢性中耳炎、感染症(おたふく風邪や細菌性髄膜炎など)、若年発症型両側感音難聴、耳の病気(耳硬化症、突発性難聴、腫瘍など)、薬剤性、外傷、加齢
3.聾(ろう)とは何が違うの?
「聞こえにくい」と「聞こえない」の境界線。
聾(ろう)は、基本的に音としての認識がほとんどできない状態。
難聴は、音そのものは入るけれど、言葉としての理解が難しい状態を指します。
時々、こんな誤解もあります。
「補聴器をつけたら、普通に(正常の人と同じレベルで)聞こえるんでしょ?」
これはよく聞かれますが、残念ながら
答えはNOです。
補聴器は、「魔法の耳」ではないんです。
補聴器は、あくまで音を聞き取りやすくしてくれる機械なだけ。
そのため、「目が悪いから眼鏡をかける」とは、似ているようでちょっと違う世界なんです。
4. デフリンピックってどんな大会?
 (画像参照元:一般財団法人全日本ろうあ連盟 スポーツ委員会)
(画像参照元:一般財団法人全日本ろうあ連盟 スポーツ委員会)
静寂の中で躍動するアスリートたち。
デフリンピックはパラリンピックとは別に開催され、聴覚障害のある選手だけが参加します。
「デフリンピック」の “デフ(Deaf)” は、英語で「ろう者(聴覚障害のある人)」を指す言葉です。
ただし、この “Deaf” には単に「聞こえない」という意味だけでなく、ろう者としての文化やアイデンティティを持つコミュニティを含む場合もあり、少し広い意味を持っています。
- Deaf(大文字):手話を第一言語とし、ろう者コミュニティに属する人。
- deaf(小文字):医学的に聴覚に障害がある状態を指すことが多い。
デフリンピック(Deaflympics)は、まさに
“Deaf(聴覚障害のあるアスリート)” のための国際スポーツ大会
という意味で名づけられています。
実は、日本と海外では「聴覚障害」の基準値が違うのを知っていますか?
- 日本:70dB以上
- 国際基準:55dB以上
この差のせいで、海外でなら出場できても日本では聴覚障害者と認められない人もいます。
そして、日本の厳しい基準値が、難聴者の生きづらさを増やす一因にもなっています。
なぜなら、身体障害者手帳などの制度基準に満たない「軽度・中等度難聴」の人でも、日常で会話が分かりづらく、生活に支障を抱えている人は多いからです。
「聞こえる」か 「聞こえない」かだけで分けられる制度だと、その間のグレーゾーンにいる人が制度の網をくぐってしまう。
これは、なかなか深刻な問題です。
それでも、静寂の世界で全力を尽くすデフアスリートたちの姿は、ただただ輝いています。
5. 私自身のこと
補聴器と一緒に歩いてきた人生。
私も生まれつきの難聴があり、幼少期から両耳に補聴器をつけて育ちました。
当初の診断名は感音難聴ですが、「少し混合難聴も混ざっているかもね」と言われたこともあります。
難聴が発覚した幼稚園の頃の検査では、軽度から中等度難聴との結果でしたが、大人になった今は高度難聴あたりになっています。
しかし、私の子ども時代は難聴児への支援はほとんどないため、幼稚園から大学までずっと普通学級でした。
授業中は前の席に座らせてもらったりしましたが、聞こえていないことが多々あったかと思います。聞き逃したかどうかも、自分では判断ができません。
とにかく人の顔を見て、口の動きを読み取って、聞こえてくる単語から言ってることを推測して、毎日を過ごしていました。
特に、女の子同士のコミュニケーションである内緒話に参加できず、さみしい思いをしたことも。
また、クラスで行うゲーム大会、水泳の授業、自然学校などのイベント時は、普段の生活とは違うイレギュラーな事が多く、周りの環境についていくのに苦労しました。
常に周囲の状況を確認しつつ、聞き取ることにも集中する必要があったため、人よりも疲れやすく、よく眠っていました。
それでも、なんとか国家資格まで取得できました。
医療系の大学に入学したことで、周囲の理解が格段に上がったことや私自身の伝える力が上手くなった結果、人とのコミニケーションが楽しくなったことを今でも覚えています。
6. 補聴器ってどんなもの?

「魔法の耳」ではなく、「助けてくれる相棒」。
補聴器は、音を大きくしたり、聞き取りやすく調整したりしてくれる機械です。
音を大きくするだけの集音器と違って高価ですが、聞こえの質は高い(自然な音として聞こえやすい)です。
しかし、雑音の多い場所は苦手です。
人間の耳の機能は、雑音を適度にカットしてくれますが、補聴器は周りのガヤガヤもまとめてパワーアップしてしまうので、聞き取りたい目的の会話までたどりつけず、迷子になることも。
また、補聴器を使う場合は、
- 壊れやすいのでケース保管を習慣に
- 定期的なフィッティング調整が大事
- 「聞こえてるつもりで、実は聞こえてない」こともある
- 環境調整(「聞きやすい&話しやすい」環境を整える工夫)を意識する
こんなポイントを知っておくと、日常が少し楽になります。
補聴器は、眼鏡のように購入してすぐに使えるようになるものではありません。
細かい調整を繰り返すことで、自分にとってベストな補聴器が出来上がります。
7. さいごに
「聴覚障害者=手話」
「補聴器や人工内耳=聞こえるようになる」
そんな単純な二分論では語れないのが、聞こえにくさの世界です。
実際には、手話だけがコミュニケーション手段というわけでもなく、補聴器をつけたからといって「聞こえる人と同じ聞こえ方になる」わけでもありません。
そのはざまにいる人たちの存在が、社会ではまだ十分に見えていないように感じます。
だからこそ大切なのは、まず自分の聞こえの特性を客観的に知ること。
そして、日常の中で「私はこういう聞こえ方なんです」と自分の言葉で説明できる力を育てることが重要だと考えています。
とくに、私のように、身体障害者手帳の対象にならない程度の難聴の場合ほど、周囲から気づかれにくく、困りごとを抱え込みやすい立場にあります。
「見えにくい困難」を伝えるには、やはり自分自身を理解し、言葉にする力が欠かせません。
聞こえの世界は、グラデーションです。
その多様さがもっと広く知られたら、子どもも大人も、いまより少し過ごしやすくなるはずです。
聴覚障害は、周りのひとことや理解で生きやすさが大きく変わります。
デフリンピックをきっかけに、聞こえにくさを持つ子どもたちや大人たちについて、
「そうなんだ、知らなかった!」と思ってもらえたら、うれしいです。
補聴器を使う子を育てているママたちが、少しでも心軽く過ごせますように。
今後も、補聴器ユーザーとしてのリアルを詳しくコラムに書いていきたいと思っています。
楽しみにしていてくださいね。
そして、いちばん伝えたいのは
「どうか一人でがんばりすぎないで」ということです。
悩んだり迷ったりするのは、あなただけじゃありません。
お子さんやご家族にとって、今いちばん大事なことは何か。どんな制度やサポートがあるのか。そして、これから成長していく中でどんなことが出てくるのか。
そんなヒントが見つかるかもしれない「絵本屋だっこ」の体験談を、ぜひ読んでみてくださいね。
コラムでは、乳幼児から成人した子どもとの暮らしについて、ママたちが回答しています。
親子ともに、心身ともに無理ない暮らしを長く続けていく方法をみんなで考えていきたいですね♪
*絵本屋だっこのコラムに関しては、全ての方に当てはまる情報ではございません。
投稿された情報の利用により生じた損害については、絵本屋だっこでは責任を負いかねます。あくまでもご家庭での判断のもと参考情報としてご利用ください。また、特定の施設や商品、サービスの利用を推奨するものではありません。
ひとりで悩んでしまう方は『絵本屋だっこ相談室』へご相談ください

絵本屋だっこでは、障害児ママたちが安心して相談できる場所をつくるため、また、障害児がいて外で働けないママたちの居場所をつくるため、『絵本屋だっこ相談室』を開設しました♪
ぜひお気軽に、ご相談にきてくださいね。
新米ママたちへ向けたお役立ち情報の掲載
こちらのコラムページでは、重心児や自閉症・発達障害などの障害児を育てる先輩ママたちにご協力いただき、新米ママたちへ向けたお役立ち情報を発信していきます!
<コラムに載せる内容例>
- 障害児ママたちの体験談まとめ【連載企画】
- 障害児向けの便利グッズ
- 障害児育児のお役立ち情報
- 障害児が使える福祉サービスについて
- 障害児の将来に関すること など……
今、子どもに障害を宣告され、不安いっぱいのママたち、まだまだ子どもが小さく先が見えず不安なママたちへ、必要な情報を届けられればと思っています。
コラム掲載のご案内は、公式LINEやインスタなどで行なっていきますので、ぜひチェックしにきてくださいね!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
▼絵本屋だっこInstagram

コラム記事を書いてみたい方を募集中!
絵本屋だっこでは、子どもに障害があって外に働きに出られないママたちの働き場所をつくる取り組みをスタートさせました。こちらのコラム記事執筆も、そのひとつです。
報酬は多くは出せませんが、お手伝いいただける方がいればぜひ公式LINEよりお問い合わせください。一緒に活躍の場をつくっていきましょう!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
ボランティアさんも募集中♪
絵本屋だっこコラムでは、障害児ママ以外にも、情報発信をしてくださる方を募集します♪
たとえば、特別支援学校の先生、リハビリの先生、デイのスタッフさんなど、障害児ママたちの不安を解消できるような情報発信をしたいという方がいましたら、ぜひご協力ください!
みなさまのあたたかなご協力をお待ちしております(^^♪