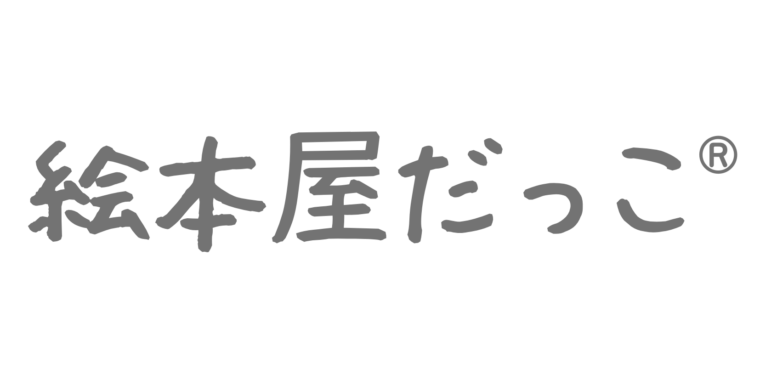絵本屋だっこでデジタルサポーターをさせていただいている「凸凹エンジニア」と申します🙇発達障害当事者です。(自閉スペクトラム症、軽度場面緘黙、聴覚情報処理障害の疑い)
前職では船の設計をしていました。設計の仕事は大好きでしたが、うつ病を発症し、その後、自閉スペクトラム症(ASD)の診断を受けました。職場での理解が難しく、退職することになりました。
私自身発達障害の当事者であるので、「発達障害」メインの記事が書ければと思います。発達障害は十人十色なので、あくまでも私の例になりますが、少しでも参考になれば幸いです。
知ってほしい、いろんな感じ方|うまく言えなくても大丈夫(吃音、チック、緘黙関係のコラム 小学生向き)
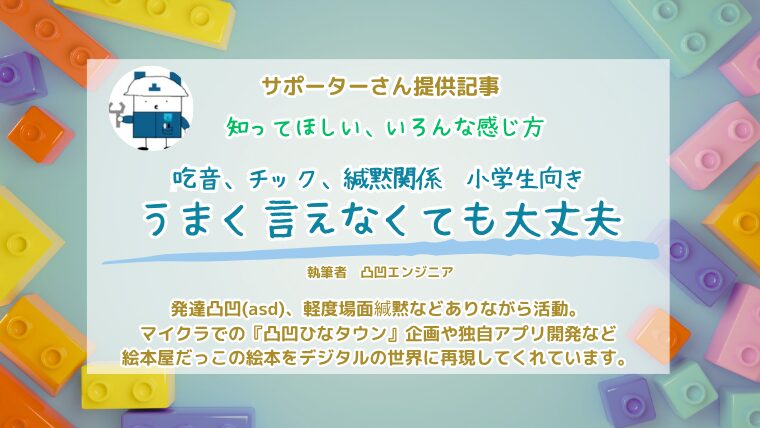
※発達障害の特性や症状の出方は十人十色です。これはあくまで私自身の記録であり、特定の誰かを批判するものではありません。
声ってむずかしい
声がうまく出ない。 話そうとすると、身体が先に反応してしまう。 咳チック、揺れ、震える声—— それでも、私は話し続けてきました。
この文章は、そんな私の“声の記録”です。 恥ずかしさも全部抱えながら、 それでも伝えたかった言葉があります。
「うまく言えなくても大丈夫。」 この声が、どもる子どもたちの未来に、 少しでも届きますように。
自分の喉がうまく使えない。
小さいころから、私は声や話し方のことでよくからかわれてきました。 「変な声」と言われたり、話し始めると笑われたり。 真似されたり。真剣に話しているのに、その“音”だけで茶化されることがありました。 自分の喉なのに、いまだにうまく使えない。 それが、ずっと続いています。
とにかく喉がうまく使えません。声が出るまでどんな声が出るか自分でもわかりません。声が高すぎたり、低すぎたり。そんなとき、周囲の人が私の言い方、声を真似するのです。
どうしても、声の高さがうまく調整できない。 自分では、ふつうに話してるつもりなのに、 出てくる声が、思ったより低かったり、 変な高さになったりする。 それを真似されると、 「ああ、また変だったんだ」って気づく。 声が、自分のものじゃないみたいに感じる。
みんなで合唱していた。 音楽室に響く声の中で、 私の声だけが、どうしても低くなる。 自分ではふつうに歌ってるつもりなのに、 出てくる声が、みんなと違う。 クラス中が振り返って、 「なんか一人だけ男の人いる〜」って笑った。 その瞬間、顔が熱くなって、 でも何も言えなくて、 次の歌詞から、私は口パクになった。 声を出すのが、怖くなった。
「さっきの歌、なんか変だったよね」って、 誰かが言って、 別の子が「低すぎて笑った〜」って返した。 名前は出てない。 でも、私の声のことだって、 なんとなくみんなわかってる気がした。
「また歌ってよ〜」って言われた。 その声が、ふざけてるようで、 どこか試してるようにも聞こえた。 私はランドセルを閉める音で、 返事をしなかった。
中学のころは、咳チックがないと話せませんでした。 言葉を出す前に、必ず咳が出る。 それがないと、声が出なかった。 自分ではどうしようもない癖でしたが、周りには奇妙に見えたようで、よく笑われていました。
ペアワーク中 「んんっ…How are you?」
「“んんっ・ハウアーユー”って何語?(笑)」
「それ、なんの合図?(笑)」
「“んんっ”がないと始まらない人(笑)」
「……」
ペアの子は笑いながら、 わざと“んんっ”を真似してきた。
そのあと、隣のペアも「んんっ・I’m fine〜!(笑)」って言い出した。
後ろの席からは「んんっ・My name is〜!(笑)」
先生が話している間も、 小さく「んんっ…」って真似する声が、あちこちから聞こえてきた。教室の中で、“んんっ”が笑いの合図みたいになっていた。 私の声の一部が、みんなの遊びになっていた。
高校では、咳チックの代わりに、声が出るまで前後に揺れる癖がありました。 無意識の動き。 それがないと、言葉が出なかった。 高校時代の友達はその癖に気づいていて、 「準備してるんだろうなぁ」と、静かに受け止めてくれていました。 そのことを思い出すと、今でも少し救われた気持ちになります。
「次は…凸凹さん」わかってた。当てられるのは。
だから、揺れていた。前へ、後ろへ。 声を出す準備。
でも、間に合わなかった。「……えっと」少し遅れて、声が出た。
その間、 誰も笑わなかった。
真似する子も、 茶化す子も、 いなかった。みんな、 私が話すのを、 そのまま待ってくれていた。
声って、 ただ出すだけじゃない。私には、 揺れて、待って、ようやく出てくるものだった。
高校時代は、 その“ようやく”を、 誰も急かさなかった。
「じゃあ、凸凹さん。次の段落を読んでください」
私は教科書を見つめて、 小さく揺れながら、声を出した。
「あっ…」 「あ、あー…」 「こ、こ…こ、この…」
声が、なかなかつかまらない。
「こ、この物語は…」 「ひ…ひと…人と…」
つまって、揺れて、 それでも、少しずつ言葉をつないだ。
教室は静かだった。
誰も笑わなかった。
先生は、ページを見ながら、 ただ待ってくれていた。
そして、 もうこれ以上は読めないと思ったとき——
先生が、 穏やかな声で言った。「よく頑張った。じゃあ、次の人」
その言葉に、 私は、すこしだけ息を吐いた。とても疲れた精神的に。
高校の時間は、 声が出るまでの「あっ」も、 「あー」も、 「こ、こ…」も、 ちゃんと待ってくれる場所だった。
声を出すことに、いつも身体が先に反応してしまう。 咳チックや揺れがないと、言葉が出ない。 そんな日々が続くうちに、 「話すことそのもの」が、だんだん怖くなっていきました。
自習中だった。 教室は静かで、 ペンの音だけが響いていた。
「んんっ…」
また出た。
なんで、こんな静かな時間に?
自分でも、わからなかった。
「んんっ…」
止めようとしても、止まらなかった。
でも、 今思えば——
静かすぎて、 息の逃げ場がなかった。
誰にも話しかけられない時間ほど、 自分の中の音があふれてくる。
「んんっ…」
まわりは、だれもわらわなかった。
でも、わたしは気になってた。
いちばん気にしてたのは、 わたしだった。
気づけば、特定の場面では声が出なくなっていました。 軽度の場面緘黙。 声を出そうとしても、喉がきゅっと閉じてしまう。 頭では「話したい」と思っているのに、 身体が「やめておこう」とブレーキをかけてくる。
そして、あるとき——
「どう思う?」って聞かれて、 あたまでは「話したい」って思ったのに、 のどがきゅってなって、 声が出なかった。
「あっ…」 「……」
口は開いてるのに、 こえがどこかにかくれてしまった。
話したいのに、話せない。
それが、 わたしの“生きてる音”と“かくれた声”だった。
それは、ただの“恥ずかしがり”ではなくて、 きっと、これまでの経験が積み重なった、 身体なりの“守り方”だったのだと思います。
声が揺れても、震えても、 伝えたい気持ちだけは、ずっと消えませんでした。今でも色々工夫しています。
<質問したいとき>
紙に質問事項を書いて、質問したい人に「これがわかりません。」と話す。
これだけでも負担が軽減します。
字が書けなければ、PCを使ってもいい。今はスマホもタブレットもある。
私は筆談と少しの声で会話しています。
どうしても、口で伝えたいときもあります。その時は、どれだけ声が変でも、チックが出ても、揺れても伝えてます。
さいごに 私みたいななやみのある子へ
話すのがこわい日もあるよね。 声が出ないとき、 まわりが気になって、つまっちゃうとき。
でもね、 あなたの声は、ちゃんと意味がある。
どんな声でも、 どんな出方でも、 それは、あなたが生きてる音。
だから、あきらめなくていい。 あなたの声を、待ってる人がいる。
もし、お友達で私のように困っている子がいる子へ
もし、教室で、 声がつまってる子がいたら、 ちょっとだけ、待ってあげてね。
その子は、いま、がんばってるところだから。
笑わないでね。
声が出るまでの「あっ…」も、 「んんっ…」も、 その子の大切な声の一部だから。
待ってくれる人がいると、 声って、ちょっとだけ出やすくなるんだ。
伝えたい気持ちのちょっとした手助けになるかも