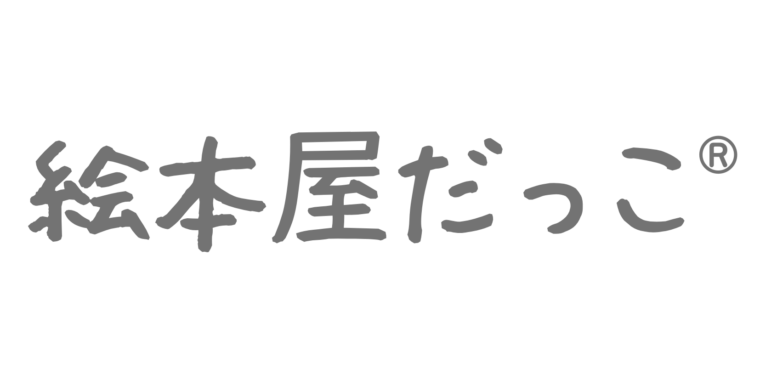こんにちは!絵本屋だっこコラム担当・相談室ピアサポーターのアイスです♪
ちょっとだけ自己紹介します。
【アイスってこんな人!】
- 寝ること・食べることが好きなアラフォー薬剤師
- 2人姉妹を育てており、次女が医療的ケア満載の重心児
- 福祉の支援やケアが必要な子の日常生活について、お母さん同士でおしゃべりしちゃう感覚でコラムを読んでもらえたら嬉しいです。
今回のコラム記事は、連載企画『ママたちの体験談』。
数年に一度と言われる大寒波が終わり、ようやく春が近づいてきましたね。
明るいイメージがある春ですが、春の初めは寒暖差・気圧差が激しいため、体調をくずしやすい時期です。また、環境の変化により、知らず知らずのうちに不安やストレスをためやすいシーズンでもあります。
春が近づくと、大人も子どもも気分が落ち着かなくなったり、ズーンとメンタルが落ちたり、理由もなく気持ちが不安定になることはありませんか?
そこで、今回のテーマは、「気持ちが不安定な時にもできる趣味や気分転換」について、アンケートをとってみました。
親子で無理なくお家での生活を過ごすために、是非ママたちの工夫を取り入れてみてくださいね。
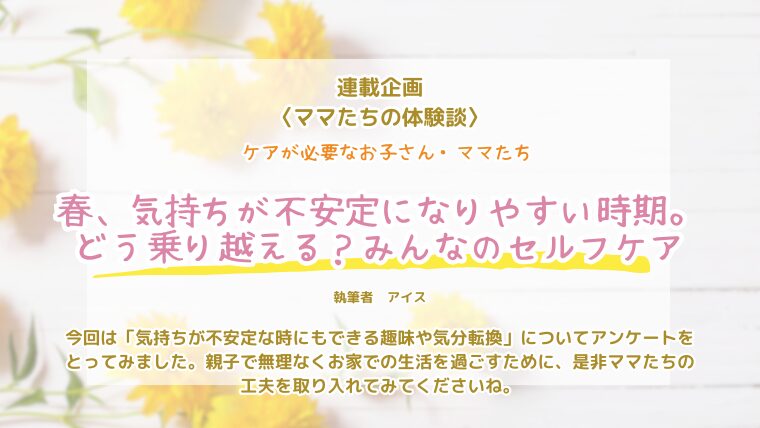
みんなのセルフケア事情~障害児ママたちの体験談~
今回は、7名の障害児ママたちへのアンケート結果をご紹介します。
ママたちには、以下の質問に回答いただきました♪
- 子どもの特性
(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ) - 子どもの年齢、性別
- 子どもが不安定になると見られる症状とその対処法
- ママが不安定になりやすいタイミング・症状とその対処法
- 気持ちが不安定な時でもチャレンジしやすいおすすめの趣味や気分転換の方法
ケース1 13歳・重心児ダウン症・男の子のセルフケア事情
 かめさんの似顔絵を描いたのは……よしのなおさん♪
かめさんの似顔絵を描いたのは……よしのなおさん♪
似顔絵サービスはこちら>>
①子どもの特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
重心
②子どもの年齢、性別
13歳、男子。
③子どもが不安定になると見られる症状とその対処法
- なんとなくソワソワしたり、体が緊張している。
→親が心配したり不安に思うと子どもの気持ちとシンクロしてしまうので、なるべくいつも通り普通に接する。
- 甘えたい時は自分から大人の手を取り頭に持って行くか、いつの間にか妙に近い所に座っている。
→子どもが出すサインに気づく。
- 初めての場所や行動に不安を持つ事が多い。
→時折「〜楽しみだねぇ。ママも初めて行くんだ〜」などと、不安を和らげる言葉を会話の中に入れてみる。
④ママが不安定になりやすいタイミング・症状とその対処法
時間に余裕が無いとき、
心身の調子が悪いとき。
- 深呼吸する。
- なるべく早く寝る。
- テレビ、SNSなどに熱中する。
- あえて毒吐き自分責めをしてみて、落ち着いたら自分褒めする(こんなんで良くやってるよ…とか)
⑤気持ちが不安定な時でもチャレンジしやすいおすすめの趣味や気分転換の方法
子どもの場合
→ひとりで出来る事を組み合わせています。
- TV・YouTubeをみる。
- 紐付き風船で遊ぶ。
- 最近押せるようになった歌の絵本で遊ぶ。
上記のことをMIXさせて、自分でバランスを取っています。
ママの場合
- 深呼吸をする。
- プチ集中出来る事をする。
私の場合は、プラバンの色を塗ったりレジン工作をしたり。
なかなか時間的に余裕がなく、出来なくなっていますが。
塗り絵やパズル、プチ手芸など、なんにも考えず没頭出来るものがやりやすいと思います。
親子共通
→散歩。
子どもが長く歩けないため短時間の散歩ですが、リフレッシュにピッタリです。
(NPO法人絵本屋だっこ理事・相談室ピアサポーターかめ)
ケース2 7歳・医ケアあり重心児・女の子のセルフケア事情
 アイスの似顔絵を描いたのは……のだそのえさん♪
アイスの似顔絵を描いたのは……のだそのえさん♪
似顔絵サービスはこちら>>
①子どもの特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
医療的ケアありの重心
(気管切開、経管栄養、夜間人工呼吸器)
②子どもの年齢、性別
7歳、女の子。
③子どもが不安定になると見られる症状とその対処法
疲れすぎたとき、季節の変わり目や雪が降る時など、激しい寒暖差・1日の気温差・気圧の変動に体がついていけない(体力的にしんどい)とき。
「いつもよりだるそう…?」と子どもの表情や体の緊張具合で判断し、親の私が気になった段階で、まずはのんびり過ごせるようにスケジュールを調整(学校は休んで、寝たい時は思う存分寝かせるなど)。
- 夜熟睡できず、寝たり起きたりを繰り返す。
- 体に力を入れて、もだえる。
→抱っこでゆらゆらしたり、いつもベッドや椅子の背もたれにくっついている背中を解放して、変に入った力を抜きやすいようにする(脱力させる方向へ)。
- 安眠効果のあるフレグランスミスト、アロマミスト、ルームフレグランススプレーを使う。(タオルにスプレーを吹きかけて、本人の枕元から少し離れたところに置く)
- 笑顔がなくなる(仏頂面のままになる)
→予定をきちんと伝える。(環境の変化に敏感なため)
スキンシップを多めにする。
- てんかん発作が増える
→必要に応じて薬を使いつつ、まずはぐっすり眠って休んでもらう。
④ママが不安定になりやすいタイミング・症状とその対処法
- 細切れ睡眠、睡眠不足。
→翌日のスケジュールに、自分の昼寝の時間を必ず確保する。
(隙あらば寝る心持ちで、睡眠不足を解消するという強い気持ちをもつ)
- 新しい環境になるときの子供のケアについての話し合い(大体、学校関係の話でストレスたまる)が進まないとき。
→最終的には、外部の支援者も巻き込んで、自分1人で抱え込まないようにする。
- PMSなどの体調が悪いとき。
→婦人科受診と薬の服用
体が冷えないように、締め付けないように、心身ともに楽を目指す。
- やらないといけないことが多すぎて、いっぱいいっぱいになるとき。
→タスクを箇条書きにして書き出す。
視覚化することで、一旦気持ちが落ち着きます。
その後、一つ一つゆっくりと削除していくために、動く感じで。
⑤気持ちが不安定な時でもチャレンジしやすいおすすめの趣味や気分転換の方法
子どもの場合
- 入浴(お風呂大好き)
- リラクゼーションミュージックを聞きながらウトウトする。
- おでこなでなで。頭を撫でられるより、眠くなるらしい。
- だっこしながら一緒にテレビを見る。
2分ぐらいで、すっと爆睡モードになります。
ただ、その後ベッドに戻そうと立ち上がると起きる…
ママの場合
- 読書
昔懐かしい漫画からエッセイ、小説、在宅ケアの本などとりあえず片っ端から読むと、気持ちが落ち着く。 - Amazon primeなどの試聴
昔観たことのある映画や趣味のホラー系を見て、頭の中を空にする時間を作ると、疲れが抜ける気がします。 - 料理
自分が食べたい物を食べたいだけ好きに作ると、ストレス発散になるみたいです。ただし、太ります… - 子ども服の整理
何故か、気持ちが落ち着きます。
(NPO法人絵本屋だっこ理事・相談室ピアサポーター アイス)
ケース3 25歳・重症心身障害者・女の子のセルフケア事情

①子どもの特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
重心(医療的ケア無し)
②子どもの年齢、性別
25歳、女子。
③子どもが不安定になると見られる症状とその対処法
- 幼少期のころ、「眠れない」症状。
→暑い/寒いなどから来ていることもあるので、室温の調節をしてみる。首元を冷やす、手足を温めるなどの直接的なアプローチに加え、そばで音楽やラジオをかけるなどして気分転換をしてみる。
- 学校時代、「歯ぎしり」あり。
→楽な姿勢にする、おやつを食べる、歯磨きするなど緊張を和らげてみる。 - 現在、「眉間にシワをよせる」ように。
→話しかける、姿勢を変える。また、てんかんの発作が多いと不快になるので、お薬に頼る(発作時の頓服薬)。
④ママが不安定になりやすいタイミング・症状とその対処法
忙しいとき、
タスクが多く頭の整理が追いつかないとき、
家族の体調不良時、
自分の時間があまり取れないとき。
- 御香を焚いたり、コーヒーを淹れたりして、良い香りに癒やされる。
- 短時間でも、眠る。
- 短時間でも、外出して気分転換をする。
- 音楽や動画を見聞きする(イヤホンで聞くことにより、音に意識を向けて気持ち切り替える)。
- 自分にとってのお休みやご褒美時間など、あえて先のスケジュールを予め作っておく(この時間だけは自分一人になれるときや、この日だけは家事も最低限にしてやりたかったことをやるなど)。
⑤気持ちが不安定な時でもチャレンジしやすいおすすめの趣味や気分転換の方法
子どもの場合
- お腹や背中に触れることで、呼吸に意識を向けてもらい、気持ちを落ち着かせる。(娘が自分でできる「心を落ち着かせる方法だよ」と、ずっと声かけして行っています)
- 座位保持椅子の位置や向きを変えたり、体勢を整えるために座りなおしたりしてみる。
- ベッド上にいる時は、姿勢を変えてみる。
(仰臥位↔腹臥位) - 好きな飲み物やおやつをとる。幼少期は、音の鳴る絵本やキーボードを触ったり、ぶら下げたおもちゃに触れたりして、鳴らして遊ぶ動きをとっていました。
また、絵本を一緒に読む(読み聞かせする)のもよく行っていました。
ママの場合
- 在宅でも、身体を大きく動かしたり筋トレ(スクワットなど)をする。
- 御香を焚いたり、コーヒーを淹れたりして、香りで気分転換をはかる。
- たまった家事に集中する。
(ひたすら洗い物や掃除などに没頭する) - 親しい人とチャットでおしゃべりする。
- 外出できるときは、ウィンドウショッピング。幼少期は、仕事から帰ってきたお父さんに子どもをお願いして、夜ドライブしたりしていました。
(どうしても家から出られない時期には助けられました)
ケース4 7歳と5歳・発達障害・男の子のセルフケア事情

①子どもの特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
発達障害(ASD/ADHD)と軽度知的
②子どもの年齢、性別
7歳と5歳、どちらも男の子。
③子どもが不安定になると見られる症状とその対処法
- 学校や保育園に行くのを嫌がり、不登校・不登園になる。
→学校は遅め登校&早め迎え。保育園はギリギリに登園&お昼寝前に迎え。 - 些細なことで泣いてしまう。
→親といる時間を意識して作り、休ませて大丈夫な時は休ませ、家で落ち着いて過ごせるようにする。
好きな事をして遊んで過ごす。
- テレビでYouTubeを見る。
- Switchで好きなゲームをする。
- 外に出て公園で思いっきり遊ぶ。
とりあえずその場の環境から一旦離れて(休んで)、自分のやりたいことをやって発散させている感じになります!
④ママが不安定になりやすいタイミング・症状とその対処法
年度末から年度初めにかけての時期。
環境も変わるため不安になりやすい。
→子どもと一緒に休む時間を作り、好きな事をしてのんびりと1日を過ごす。
⑤気持ちが不安定な時でもチャレンジしやすいおすすめの趣味や気分転換の方法
子どもの場合
好きなゲームをやりながら、話したいだけ親に話をして聞いてもらう。
気分転換になるらしいです(自分のことを聞いてもらえるため、楽しくなるらしい)。
ママの場合
気持ちを落ち着かせるために、刺繍などハンドメイドにチャレンジします!
子どものものを作って、子どもに喜んでもらえるだけで嬉しくなります!
(サポートスタッフ うづき)
ケース5 10歳・医ケアあり・女の子のセルフケア事情

Naoさんの似顔絵を描いたのは……ノアさん♪
似顔絵サービスはこちら>>
①子どもの特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
重心、医療的ケア児
(気管切開、胃ろう、夜間人工呼吸器)
②子どもの年齢、性別
10歳、女の子。
③子どもが不安定になると見られる症状とその対処法
- 怒って泣く→痰や鼻水が増えてゼコゼコ→吸引多くなる→吸引して怒るのループ。
→好きな歌を聞かせる。
(不思議と「オバケなんてないさ」が小さい頃から好きで、落ち着きます)
→怒ってる原因を聞いてみたり考えてみたりして、原因を取り除けるように対応をする。(暑い?今は座りたくない?オムツ変えて欲しい?など試してみる)
- 体調不良時や気圧の変化がある時は、眠りがちになる。
→本人のペースでゆっくり休ませる。
④ママが不安定になりやすいタイミング・症状とその対処法
- やることに追われて時間がないとき、イライラしがちになる。
→好きな飲み物とスイーツを食べて一旦落ち着く。
よくやってる!と、自分を心の中で褒める。
優先順位を決めて、全てやろうとしない。
- 学校やデイなどとのやりとりが上手く行かないとき。
→他のママたちと気持ちを共有する。
どうしたら伝わるのか、作戦を考える。
⑤気持ちが不安定な時でもチャレンジしやすいおすすめの趣味や気分転換の方法
子どもの場合
- 音楽を聴く。
- お気に入りのぬいぐるみで遊ぶ。
- 胸や手に優しく触れて、タッチケアをする。
ママの場合
- ストレッチやヨガをする。
- アロマを垂らした湯船に、ゆっくりと浸かる。
- 好きな飲み物とスイーツで一息つく。
- 外の空気を吸う。(外に出られなくてもベランダに出る)
- セルフタッチをする。
- 1人の時間を作る。
私はタッチケア講師をしています。
タッチは、親子共に、触れる方も触れられる方も心身が落ち着き、不安やストレスの軽減・気持ちの切り替えなど、たくさんの効果が期待できます。
私自身、日常の中でその効果を実感しています。
タッチはお守りです。
ケース6 9歳・発達障害・女の子のセルフケア事情

①子どもの特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
発達障害
②子どもの年齢、性別
9歳、女の子。
③子どもが不安定になると見られる症状とその対処法
- 頑固になる。
- 不機嫌になる。
- 些細なことでイライラする、泣く。
→予定に無理がないようにする。
なるべく自分で気持ちを立て直せるようにしたいと考えています。
自力でできない時でも、まず「どうしたいのか?」とたずねてみる。
④ママが不安定になりやすいタイミング・症状とその対処法
生理前の時期、
子どもの不機嫌があるとき。
→生理前はなるべくゆっくり過ごすか、寝る!
子どもの不機嫌から敢えて意識をそらして、少しでもいい気分を保つようにする。
(安全を確認した上で、少しトイレにこもって深呼吸したり、アロマ・散歩・ストレッチ・笑える動画を見る・絵を描くなどをしてみる)
⑤気持ちが不安定な時でもチャレンジしやすいおすすめの趣味や気分転換の方法
親子ともに、外の空気を吸う。
散歩、ドライブ、買い物など。
朝のお日さまを浴びて、日光浴をする。
光を浴びながら深呼吸を3回するだけでも、気分転換になります。
ケース7 13歳・重心児・男の子のセルフケア事情
 しょうじあいかの似顔絵を描いたのは……障害者アーティスト立藤絆吏さん♪
しょうじあいかの似顔絵を描いたのは……障害者アーティスト立藤絆吏さん♪
似顔絵サービスはこちら>>
①子どもの特性(医療的ケア/重心/発達障害から選ぶ)
重心
②子どもの年齢、性別
13歳、男の子。
③子どもが不安定になると見られる症状とその対処法
- ご飯を食べなくなる。
- 表情が乏しくなる。
- 反応が鈍くなる。
普段はマイペースな息子ですが、体調不良のときやてんかんの調子が悪いときは元気がなくなります。
気持ちを言葉にできないので、何か普段と違うという、母の直感を大事にしています。
体調が悪そうなときは、無理せず家でゆっくり過ごすようにしています。
④ママが不安定になりやすいタイミング・症状とその対処法
- やることに追われて忙しいとき
→マルチタスクでバタバタしていると、気持ちの余裕がなくなります。
- 家族がイライラしているとき
→他の人の不機嫌に影響されやすい性格です。つられて自分までイライラしたり落ち込んだりしてしまいます。
- 生理前/寝不足のとき
→ホルモンバランスや睡眠不足にわかりやすく影響を受けます。自分でわかっていると、対処もしやすくなります。
⑤気持ちが不安定な時でもチャレンジしやすいおすすめの趣味や気分転換の方法
- 最低8時間は寝る
→睡眠命。子どもと一緒に8時には布団に入ります。
- 自分を責めない
→ホルモンバランスのせいだ、忙しいせいだなど、自分でないようなイライラは何か原因があります。大事なのは、自分を責めないこと。悪い思考に陥らないようにします。
- お散歩、ヨガ、ものづくり、お絵描き、庭いじり
→頭の中が思考で落ち着かないときは、手や足、体をつかうと思考をストップできます。何か没頭できるものを見つけると、ストレス解消になります♪
運動ならゆっくり深呼吸ができるストレッチ系のヨガがおすすめ。YouTubeで動画を探せます。
【みんなのセルフケア事情-障害児ママたちの体験談】まとめ
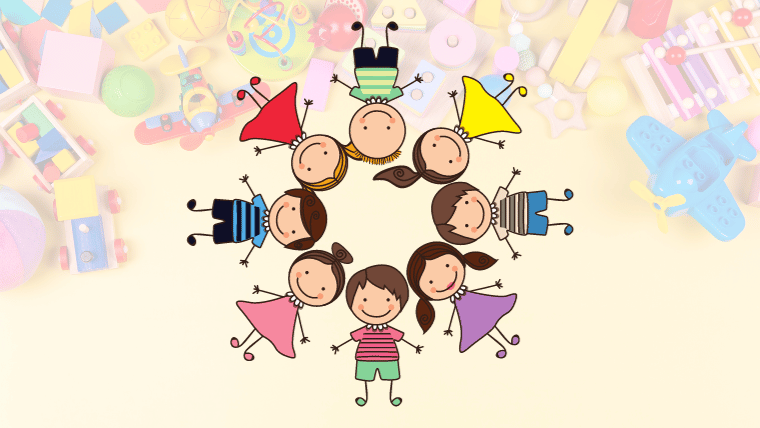
体験談を書いてくれたママたちの子供の年齢も障害もさまざまです。
子どもの状態はそれぞれ違っても、ケアの方法についてはお互い参考になるところがあるかと思います。
自分で自分の機嫌を取るにも、まずは親子共に体調が安定していることと、リラックス・リフレッシュできる時間を作る必要があります。
障害児ママたちは、子どものケアに加え、子どもの代理人として細々としたタスク(やるべき仕事・作業)が次から次へと出てくると思います。
1人で抱え込まず、誰かに依頼できるところは依頼し、わずかな隙間時間にでも自分のための時間を作るように意識してくださいね。
赤ちゃんから成人した後のケアまで幅広くコラムに書いていますので、ぜひ参考にして下さい。
親子共に少しでも休息する時間が増えますように。
体の疲れが取れて、笑顔で過ごす時間が増えますように。
私は一人じゃないんだ。と感じてもらえたら、私もうれしく思います。
NPO法人絵本屋だっこ理事・相談室ピアサポーター アイス
ひとりで悩んでしまう方は『絵本屋だっこ相談室』へご相談ください

絵本屋だっこでは、障害児ママたちが安心して相談できる場所をつくるため、また、障害児がいて外で働けないママたちの居場所をつくるため、『絵本屋だっこ相談室』を開設しました♪
ぜひお気軽に、ご相談にきてくださいね。
新米ママたちへ向けたお役立ち情報の掲載
こちらのコラムページでは、重心児や自閉症・発達障害などの障害児を育てる先輩ママたちにご協力いただき、新米ママたちへ向けたお役立ち情報を発信していきます!
<コラムに載せる内容例>
- 障害児ママたちの体験談まとめ【連載企画】
- 障害児向けの便利グッズ
- 障害児育児のお役立ち情報
- 障害児が使える福祉サービスについて
- 障害児の将来に関すること など……
今、子どもに障害を宣告され、不安いっぱいのママたち、まだまだ子どもが小さく先が見えず不安なママたちへ、必要な情報を届けられればと思っています。
コラム掲載のご案内は、公式LINEやインスタなどで行なっていきますので、ぜひチェックしにきてくださいね!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
▼絵本屋だっこInstagram

コラム記事を書いてみたい方を募集中!
絵本屋だっこでは、子どもに障害があって外に働きに出られないママたちの働き場所をつくる取り組みをスタートさせました。こちらのコラム記事執筆も、そのひとつです。
報酬は多くは出せませんが、お手伝いいただける方がいればぜひ公式LINEよりお問い合わせください。一緒に活躍の場をつくっていきましょう!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
ボランティアさんも募集中♪
絵本屋だっこコラムでは、障害児ママ以外にも、情報発信をしてくださる方を募集します♪
たとえば、特別支援学校の先生、リハビリの先生、デイのスタッフさんなど、障害児ママたちの不安を解消できるような情報発信をしたいという方がいましたら、ぜひご協力ください!
みなさまのあたたかなご協力をお待ちしております(^^♪