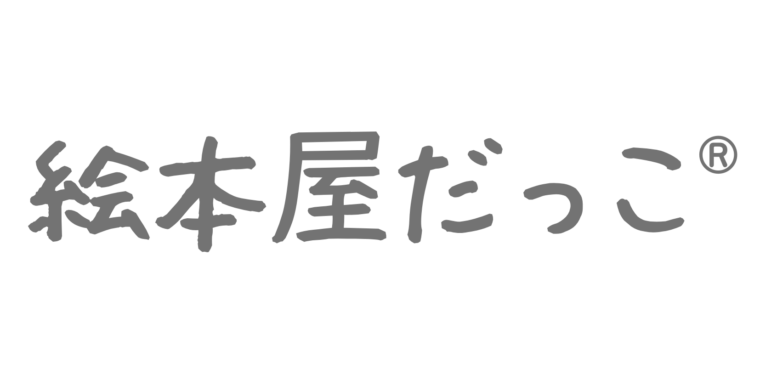こんにちは!絵本屋だっこコラム担当・相談室ピアサポーターのアイスです♪
ちょっとだけ自己紹介します。
【アイスってこんな人!】
- 寝ること・食べることが好きなアラフォー薬剤師
- 2人姉妹を育てており、次女が医療的ケア満載の重心児
- 福祉の支援やケアが必要な子の日常生活について、お母さん同士でおしゃべりしちゃう感覚でコラムを読んでもらえたら嬉しいです。
(※運営の事情によりアップが遅くなりました)
この夏は「ママのケア」も忘れずに②専門家に聞く!睡眠と食事で夏バテ予防
ようやく夏が終わりに近づいていますね。
夜間ケアや通院、家事育児でフル稼働している障害児ママにとって、夏バテは大敵。
自分の体調が崩れると子どものケアにも影響が出てしまうため、早めの予防が大切です。
ただの疲れだと思って放っておくと、体力や気力をさらに奪い、ケアにも影響してしまいます。
今回は、薬剤師&睡眠コンサルタントの資格をもっているアイスが、それぞれの専門的な視点から「夏バテを予防する工夫」を詳しくお届けします。

1.夏バテが起こる理由
夏バテとは、夏の高温多湿の環境による体調不良の総称です。
夏バテは、単なる「疲れ」ではなく、
- 眠りが浅くなる
- 食欲が落ちる
- 体力が奪われる
といった悪循環を招きます。
主な原因は、次の3つ。
- 水分・塩分(ミネラル)不足
- 食欲減退・栄養不足
- 自律神経の乱れ
屋外の暑さと室内の冷房を行き来することで、自律神経が疲れてしまい、睡眠や消化に影響が出ます。
障害児ママはもともと不規則な生活になりやすいので、この3つが重なると、夏バテの影響を強く受けやすいのです。
ここでは、夏バテの原因と具体的な予防法(対策)についてご紹介します。
1-1.水分とミネラル不足
汗をかくことで体内の水分やナトリウム、カリウムなどのミネラルが失われやすくなります。
体の中の電解質バランスが崩れると、倦怠感、めまい、頭痛、食欲不振などが、夏バテの症状として現れます。
医学的には、体内の水分とミネラルが不足すると血液の循環が悪くなり、脳や筋肉に必要な酸素や栄養が届きにくくなります。
また、脱水状態では体温調節もスムーズにできなくなり、熱中症のリスクも高まります。
障害児や医療的ケア児は、体温調節機能が弱いことに加えて、発汗量や水分補給量の管理が難しい場合があります。
そのため、ママが意識的に水分やミネラルを補給するサポートをすることがとても重要です。
ママ自身も、夜間のケアや忙しい日常でこまめな水分補給を忘れがちです。
脱水気味の体で日中を過ごすと、疲労や集中力低下、夏バテ症状がさらに強くなることがありますので注意です。
以下に、夏バテを防ぐための水分・ミネラル補給の工夫をお伝えします。
①こまめに水分を摂る
一度にたくさん飲むより、少量を何回かに分けて。
経口補水液や麦茶、スポーツドリンクなども活用できます。
②ナトリウム・カリウムの補給
塩少々を加えた麦茶や味噌汁、果物(バナナ、キウイなど)でミネラルを補給。
汗で失われた電解質を補うことで、体力の低下やだるさを防ぎやすくなります。
③無理に冷たい飲み物は摂らない
冷たい飲み物の摂りすぎは胃腸を冷やして消化機能を低下させます。
温かい飲み物や常温の水も取り入れましょう。
- 水分とミネラルは「こまめに少しずつ」が基本
- ママも子どもも意識的に補給することが大切
- 脱水を防ぐことで、夏バテだけでなく熱中症リスクも下げられる
1-2.消化機能の低下と栄養不足

暑い日が続くと、冷たい飲み物やアイス、そうめんや冷麺などの食事が増えがちではないでしょうか?
つい手軽に済ませてしまうことも多いですよね。
しかし、冷たいものの取りすぎは 胃腸を冷やして消化機能を低下させるため、体が必要な栄養をうまく吸収できなくなります。
医学的には、消化器官の温度が下がると消化酵素の働きも弱くなり、栄養の吸収効率が落ちることがわかっています。
その結果、体力が十分に回復せず、だるさや眠気、夏バテの症状が出やすくなるのです。
さらに、医療的ケア児や障害児の場合、もともと摂取できる食事量が限られていたり、嚥下や消化の機能に制限があったりすることがあります。
つまり、「必要な栄養が不足しやすい」状態がさらに加速しやすいのです。
また、ママ自身も夜間のケアや通院で食事が不規則になりがち。
栄養不足や食事の偏りが続くと、自律神経の働きも乱れやすくなり、体力低下や免疫力の低下につながります。
ここからは、夏バテを防ぐための食事の工夫をお伝えします。
①冷たいものは、ほどほどに
冷たい飲み物やアイスは、胃腸を冷やし、胃腸の働きが悪くなります。
温かいスープやお味噌汁、発酵食品(納豆、ヨーグルトなど)を意識して取り入れましょう。
カフェインのとりすぎにも注意。
②栄養バランスを意識
- タンパク質:疲労回復に必要(肉、魚、大豆製品)
- ビタミンB1:糖質をエネルギーに変える(豚肉、玄米)
- ミネラル:汗で失われやすいナトリウム・カリウム・マグネシウム(野菜、バナナやキウイなどの果物、発酵食品)
- ビタミンC、リコピン(トマトなど):免疫力のサポート
③無理せず、少しずつ
栄養補給を意識することで、少量ずつの食事でも消化負担を減らしながら体力回復につなげられます。
- 「冷たい」「手軽」だけの食事にならないように工夫
- 子どもとママ、どちらも栄養不足にならないように意識
- 夏バテ対策は、「消化を助ける+必要な栄養をとる」の両方が大事
1-3.自律神経の乱れ(体温調節がうまくいかない)
暑さに負けないためには、体がうまく体温を調節できるかどうかが大切です。
普段、私たちの体は汗をかく、血流を皮膚に集めるなどの働きで、体温を一定に保とうとしています。
でも、暑さが長く続いたり、冷房との温度差が大きかったりすると、この仕組みがうまく働かなくなり、体に大きな負担がかかります。
とくに、医療的ケア児や障害児は、
- 体温調節の機能が未熟
- 自律神経の働きが弱い
- 体力やエネルギーの消耗が早い
といった特徴があるため、一般的な子どもより暑さや寒さの影響を強く受けやすいのです。
医学的にみても、体温調節には「自律神経(交感神経と副交感神経)」が深く関わっています。
この切り替えがうまくいかないと、汗が出にくくなったり、逆に出すぎて体力を消耗したりして、夏バテにつながります。
だからこそ、家庭でできる工夫がとても大切です。
- 冷房を使いながらも冷えすぎない工夫
- こまめな水分補給を心がける
- 衣服やガーゼ(掛け物)での体温調整
- 外出時は帽子や日傘で直射日光を避け、室内外の温度差を少なくする
- 汗をかいたらこまめに拭き取り、服や寝具を乾いた状態に保つ
こうした小さなサポートが、子どもの体を守り、ママ自身の安心にもつながっていきます。
2.暑いと眠くなるのはなぜ?

午後、子どもを見ていたら自分もウトウト…
「なんでこんなに眠いんだろう?」と感じたこと、ありませんか?
実は、暑さの中で眠くなるのは自然な体の反応なんです。
体は熱を逃がすために汗をかき、血管を広げて、体温を下げようとします。
そのとき、副交感神経を働かせたり、血液を皮膚に集めようとする分、脳への血流は少し減ってしまいます。
結果、体がだるく感じたり、眠気が強く出たり、頭がぼんやりして、眠気スイッチが入ります。
さらに、暑さとの戦いは思った以上にエネルギーを消費します。
ママも子どもも、知らないうちに体はお疲れモードになってしまうんです。
夏から秋にかけては、室内外の温度差で自律神経が乱れやすい時期です。
自律神経の乱れは睡眠の質の低下に繋がり、結果として、疲れが上手くとれずに日中に眠気を感じることが多くなります。
ただし、この眠気は「ぐっすり眠れている」わけではなく、浅い眠りで疲れがとれていないのが特徴。
また、体温調整機能が低下すると、熱中症のリスクも高まります。
眠気だけでなく、めまいや吐き気など熱中症の症状を伴う場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
3.睡眠コンサルタント直伝!快眠のための工夫
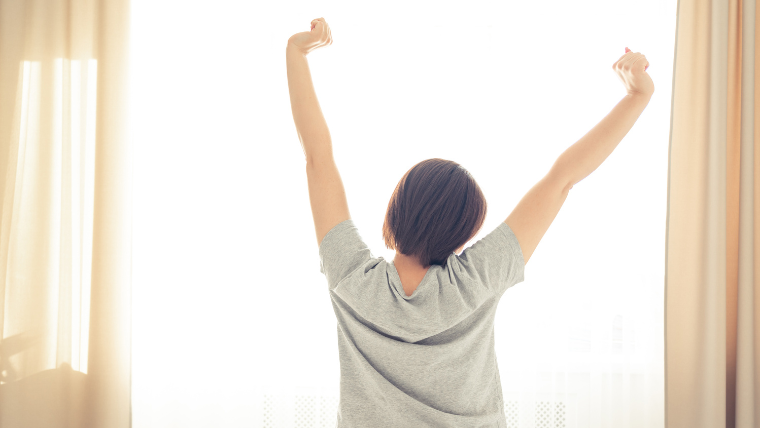
夜間のケアで、長く眠れないママも多いですよね。
だからこそ、「短時間でもぐっすり休める環境づくり」が夏バテ予防のカギになります。
3-1.寝室環境を整える
エアコンは27〜28℃が目安。
扇風機やサーキュレーターで空気を循環させましょう。
3-2.お風呂で体温リセット
寝る1〜2時間前に、38〜40℃のお湯に10〜15分入り、リラックス。
深部体温が下がり、自然と眠りやすくなります。
3-3.生活リズムを崩さない
朝「起きる時間」を一定にすると、体内時計が整います。
遮光カーテンで明るさを調整したり、入浴で眠りのスイッチを入れると、短時間の睡眠でも疲労回復につながりやすいです。
3-4.簡単なストレッチ
- 身体を動かして、体温を上げる。
- 息を吸う回数を多めに深呼吸する。
息を吸うときは交感神経・息を吐くときは副交感神経が刺激されるので、自律神経を整えるために、ストレッチは有効です。
3-5.朝食のポイント
大人は、その日の体調に応じて判断をしてもオッケー。
眠気を追い払うためには、朝に甘いものを食べることが効果的です。
消化器系を動かすことで体内時計をリセットでき、また、甘いものは脳の動きを活発にします。
きのうは食べ過ぎたな…と感じている朝でも、ヨーグルトにフルーツを入れて食べるぐらいなら、余分なカロリーを摂らずに、体内時計をリセットすることもできます。
4.秋に持ち越さないために
夏の疲れは、秋まで持ち越すことがあります。
涼しくなっても眠気やだるさが続く場合は、いわゆる「秋バテ」と呼ばれる状態かもしれません。
秋バテは、主に自律神経の乱れや夏の栄養不足が原因とされています。
- 体がだるい
- やる気が出ない
- 頭が重い
などの症状が出たら、 なるべく休む時間を作ること、温かい食事やお風呂で自律神経を整えることが大切です。
5.おわりに
夏バテ予防のポイントは、
「しっかり眠ること」と「正しく栄養をとること」。
障害児ママは、ただでさえ日々のケアや通院で体力も気力も使っています。
自分の睡眠や食事が、どうしても後回しになりがち。
「眠い=なまけてる」ではなく、「眠い=体からのSOS」。
まずは水分をとって、5分でも目を閉じる時間をつくってください。
ママが元気でいることが、子どもにとっていちばんの安心です。
まずは「できることから一つ」。
ママの元気が、子どもの笑顔につながります。
そして、いちばん伝えたいのは
「どうか一人でがんばりすぎないで」ということです。
悩んだり迷ったりするのは、あなただけじゃありません。
お子さんやご家族にとって、今いちばん大事なことは何か。どんな制度やサポートがあるのか。そして、これから成長していく中でどんなことが出てくるのか。
そんなヒントが見つかるかもしれない「絵本屋だっこ」の体験談を、ぜひ読んでみてくださいね。
コラムでは、乳幼児から成人した子どもとの暮らしについて、ママたちが回答しています。
親子ともに、心身ともに無理ない暮らしを長く続けていく方法をみんなで考えていきたいですね♪
*絵本屋だっこのコラムに関しては、全ての方に当てはまる情報ではございません。
投稿された情報の利用により生じた損害については、絵本屋だっこでは責任を負いかねます。あくまでもご家庭での判断のもと参考情報としてご利用ください。また、特定の施設や商品、サービスの利用を推奨するものではありません。
ひとりで悩んでしまう方は『絵本屋だっこ相談室』へご相談ください

絵本屋だっこでは、障害児ママたちが安心して相談できる場所をつくるため、また、障害児がいて外で働けないママたちの居場所をつくるため、『絵本屋だっこ相談室』を開設しました♪
ぜひお気軽に、ご相談にきてくださいね。
新米ママたちへ向けたお役立ち情報の掲載
こちらのコラムページでは、重心児や自閉症・発達障害などの障害児を育てる先輩ママたちにご協力いただき、新米ママたちへ向けたお役立ち情報を発信していきます!
<コラムに載せる内容例>
- 障害児ママたちの体験談まとめ【連載企画】
- 障害児向けの便利グッズ
- 障害児育児のお役立ち情報
- 障害児が使える福祉サービスについて
- 障害児の将来に関すること など……
今、子どもに障害を宣告され、不安いっぱいのママたち、まだまだ子どもが小さく先が見えず不安なママたちへ、必要な情報を届けられればと思っています。
コラム掲載のご案内は、公式LINEやインスタなどで行なっていきますので、ぜひチェックしにきてくださいね!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
▼絵本屋だっこInstagram

コラム記事を書いてみたい方を募集中!
絵本屋だっこでは、子どもに障害があって外に働きに出られないママたちの働き場所をつくる取り組みをスタートさせました。こちらのコラム記事執筆も、そのひとつです。
報酬は多くは出せませんが、お手伝いいただける方がいればぜひ公式LINEよりお問い合わせください。一緒に活躍の場をつくっていきましょう!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
ボランティアさんも募集中♪
絵本屋だっこコラムでは、障害児ママ以外にも、情報発信をしてくださる方を募集します♪
たとえば、特別支援学校の先生、リハビリの先生、デイのスタッフさんなど、障害児ママたちの不安を解消できるような情報発信をしたいという方がいましたら、ぜひご協力ください!
みなさまのあたたかなご協力をお待ちしております(^^♪