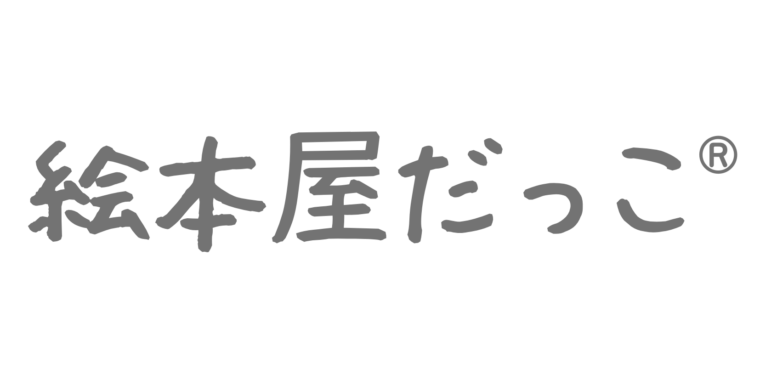こんにちは!絵本屋だっこコラム担当・相談室ピアサポーターのアイスです♪
ちょっとだけ自己紹介します。
【アイスってこんな人!】
- 寝ること・食べることが好きなアラフォー薬剤師
- 2人姉妹を育てており、次女が医療的ケア満載の重心児
- 福祉の支援やケアが必要な子の日常生活について、お母さん同士でおしゃべりしちゃう感覚でコラムを読んでもらえたら嬉しいです。
療育ってなに? はじめての療育ガイド① 療育の基本情報
「発達に少し遅れがありますね。手術が一旦落ち着いた今のタイミングで、病院で受ける体のリハビリ(PT)と地域で受ける療育をやっていきませんか?」
わが子が生後半年を過ぎたころ、医師からそう言われました。
先天性の疾患があることはわかっていたけれど、「療育」という言葉を聞いたのはそのときが初めて。
何をする場所なのかも分かりませんでした。
「本当に必要なの?」
「この子は、そんなに大変な子なの?」
戸惑いと不安でいっぱいだったのを覚えています。
今回は、療育に関する基本的な知識とともに、わが子が療育を受けるまでの流れを、実体験も交えながら、できるだけわかりやすくお伝えします。

1.療育とは?
文字の通り、「医療(からだやこふころのケア)」と「教育(学びや生活のサポート)」を組み合わせて行うものです。
1-1.療育の定義
療育とは、発達に特別なサポートが必要な子どもが、できることを少しずつ増やしていけるように支援することです。
「療育」と似た意味で使われる言葉に「発達支援」があります。
本来、「療育」という言葉は、身体障害のある子どもを対象とする支援から生まれた言葉です。
近年は、身体以外の障害や困難を対象とする支援にも広がりました。
そのため、現在では、「療育」と「児童発達支援」がほぼ同じ意味合いで使われていることが多いようです。
・「療育」は、発達を支えるための取り組み・考え方
・「児童発達支援」は、療育を行う具体的な福祉サービス(未就学児向け)
1-2.どんな子が対象なの?
療育の対象となるのは、身体または知的な障害(発達障害も含む)がある18歳以下の子どもです。
手帳の有無にかかわらず、発達の遅れや心配事のある子どもも療育の対象となります。
例えば、こんな子どもたちも対象になります。
- 発達に特性がある子(例:ことばが遅い、落ち着きがないなど)
- 知的な障害や自閉スペクトラム症(ASD)などの診断がある子
- 医療的ケアが必要で、生活面でサポートが必要な子
2.療育の目的・支援内容
療育は、子どもの「できる」を少しずつ増やしていくサポートです。
療育の主な支援は、大きく分けて4つあります。
- 子どもの発達をうながす活動
- 日常生活の練習
- 家族へのサポート
- 医学的・専門的なサポート(必要に応じて)
2-1. 子どもの発達をうながす活動
言葉がゆっくりだったり、体の使い方が不器用だったり…
子どもの年齢や特性に合わせて、遊びを通じて学ぶ活動をします。
たとえば、以下のような活動が行われます。
- お友達とのやりとり(社会性)
- ことばのやりとり(コミュニケーション)
- 手先を使うあそび(手先の発達)
- 体を動かす活動や感覚遊び(運動機能)
2-2. 日常生活の練習
ごはんを食べる、服を着替える、トイレに行くなど、日常生活に必要な動作を練習します。
2-3. 家族へのサポート
療育は、子どもだけのためのものではありません。
子どもの関わり方や家庭での工夫を、一緒に考えたりアドバイスしたりしてくれます。
保護者が、子どもの特性を理解したり、子育ての悩みを話せる場所でもあります。
「わかってくれる人がいる」
それだけで、心がふっと軽くなることもありますよね。
2-4.医学的・専門的なサポート(必要に応じて)
言語聴覚士(ST)、作業療法士(OT)、理学療法士(PT)などの専門職が、リハビリ的な支援を行うこともあります。
3.療育の効果
療育は、「困っていることをなくす」だけでなく、「その子らしい育ちを応援する」もの。
発達に困りごとがある子どもは、「できないこと」だけを見られてしまいがちです。
でも、早い時期に適切なサポートを受けることで、その子らしい力が育ち、自信や社会とのつながりを築く手助けになります。
私自身、療育に対して「障害の程度が良くなる」といったイメージよりも、「子どものいいところを見つけて伸ばしてもらえる場所」「できることを少しずつ広げていける場所」と考えています。
家族だけでがんばろうとすると、つい視野が狭くなってしまうこともあります。
療育は、外部からの客観的な目で子どもを見てもらえる、そして親自身も新しい気づきをもらえる、そんな貴重な場だと思っています。
4.療育を受けるには
療育を受けるきっかけは、多岐にわたっています。
わが家の場合は、小児科で発達の遅れを指摘されたのがきっかけでした。
1歳まで病院のリハビリに通い、地域に移行していくタイミング(うちの地域では、1歳前後を目安にしているそう)で、地域へ相談をするように病院からアドバイスがありました。
そこから、福祉課に相談に行き、地域の相談員(障害福祉サービスの相談員・相談支援専門員)につながりました。
ここからは、一般的な流れについて紹介します。
4-1.相談
発達の心配があっても、「こんなことで相談していいのかな」と迷ってしまうこと、ありますよね。でも、専門機関は早めの相談を歓迎してくれます。
相談できる場所は、意外とたくさんあります。
- かかりつけの小児科
- 乳幼児健診の保健センター
- 市区町村の福祉課
- 地域の子育て支援センター
- 保育園、幼稚園、学校など
4-2. 必要に応じて、発達検査や診察
実は、療育を受けるべきかどうかの明確な基準はないのを知っていますか?
障害者手帳の取得や医学的な診断も、必須条件ではありません。
療育の対象となるのは、医師や保健所・保健センターなどにより支援の必要性が認められた場合です。
相談の内容によっては、発達検査や小児神経科などの診察を勧められることもあります。
これにより、子どもの今の発達の様子が整理され、療育の必要性についてもより具体的に見えてきます。
4-3. 「通所受給者証」の作成・申請・発行
療育サービスを利用する場合には、居住地の自治体より発行される受給者証が必要です。
「通所受給者証」という福祉サービスの証明書のことです。
この受給者証をもらうには、まず相談支援専門員と面談をして、サービス等利用計画という計画書を作ってもらいます。
ちょっと構えてしまう名前ですが、家庭の状況や子どもの様子を一緒に振り返って整理してくれる、とても心強い存在です。
保護者が自分で利用計画を作るセルフプランのやり方もあります。
計画書ができたら、それをもとに自治体に「通所受給者証」の申請をします。
申請後、審査を経て受給者証が発行されるまで、数週間かかることもあるので、早めの動き出しが安心です。
4-4.療育施設の見学&選定
受給者証の発行が見えてきたら、いよいよ施設選び。
わが家も何か所か見学して、「ここなら楽しんで通えそう」と思える場所に出会えました。
4-5.契約&療育スタート!
契約手続きを済ませたら、いよいよ療育が始まります。
少しずつ子どもの笑顔や表現のバリエーションが増えたり、友達との関わりが増えていく姿を見て、「療育を受けて良かったな」と思えるタイミングが来ます。
5.療育を受けられる場所
「療育」とひとことで言っても、その内容や方法は本当にさまざまです。
子どもの障害の状態や暮らし方によって、必要な支援も変わってきます。
だからこそ、「どんな療育施設を」「どれくらいの頻度で」利用するかは、それぞれのご家庭で違います。
療育を受ける方法には、大きく分けて次の3つのパターンがあります。
- 障害福祉サービスを利用する場合
- 医療の一環として療育を受ける場合
- 民間の療育プログラムやオンラインサービスを利用する場合
療育を受けられる場所も複数あります。
5−1.障害福祉サービスを利用する場合
福祉の制度を利用して療育を受ける方法です。
通所(通う)・訪問(来てもらう)・入所(施設で過ごす)の3つのタイプがあります。
通所と訪問を組み合わせて使っているご家庭も多いです。
① 通所型(施設に通う)
- 児童発達支援センター(療育園)
- 児童発達支援事業所
- 放課後等デイサービス など
②訪問型(家に来てもらう)
訪問型では、自宅で療育を行ないます。
③入所型(施設で暮らしながら受ける)
障害児入所施設(福祉型・医療型)に入所したケースでも、施設内で療育をうけられます。
ただし、施設入所は、虐待や精神疾患など何かしらの理由があり、「親が保育を行うことが難しい」と判断されなければ、一般的には施設入所とはなりません。
5−2. 医療の一環として療育を受ける場合
病院や療育センターなど、医療機関でリハビリなどの療育を受けることもあります。
この場合、「医療」として必要だと判断されれば、障害児通所受給者証がいらないケースもあります。
5−3. 民間の療育プログラムやオンラインサービスを利用する場合
最近では、民間の事業者が行う療育プログラムや、オンラインでの支援サービスも増えています。
こちらは公的な支援ではないため、料金は自由に設定されていて、利用料は自己負担になります。
6.おわりに
「療育」とは、特別なことをする場所ではありません。
その子がその子らしく、安心して育っていけるように、ちょっとした後押しをする場所。
誰かと比べなくていい。
「この子にはこの子の歩む道がある」と、今は心からそう思えます。
迷いながらでも大丈夫。
あなたが「ちょっと相談してみようかな」と思ったその一歩が、きっと大切な始まりになります。
そして、「うちの子に療育って必要なのかな?」と迷っている方に伝えたいのは、「相談すること=療育が決まる」わけではないということ。
相談の先に必要なサポートがあるかどうかを見つけるだけでも、大きな意味があります。
最初の一歩は、きっと勇気がいります。
でも、その一歩が、子どもと家族の未来を少しずつ明るくしてくれるきっかけになるかもしれません。
この療育に関するコラムには続きがあります。
次回は、いくつかの療育を経験してきたわが子の実例をもとに、施設の選び方や「療育」と「保育」の違い、そして実際に利用して感じた各療育の特徴についてご紹介します。
子ども目線だけでなく、保護者として感じたメリットやデメリットについても率直にお伝えする予定です。
どうぞお楽しみに!
そして、いちばん伝えたいのは
「どうか一人でがんばりすぎないで」ということです。
悩んだり迷ったりするのは、あなただけじゃありません。
お子さんやご家族にとって、今いちばん大事なことは何か。どんな制度やサポートがあるのか。そして、これから成長していく中でどんなことが出てくるのか。
そんなヒントが見つかるかもしれない「絵本屋だっこ」の体験談を、ぜひ読んでみてくださいね。
親子ともに、心身ともに無理ない暮らしを長く続けていく方法をみんなで考えていきたいですね♪
*絵本屋だっこのコラムに関しては、全ての方に当てはまる情報ではございません。
投稿された情報の利用により生じた損害については、絵本屋だっこでは責任を負いかねます。あくまでもご家庭での判断のもと参考情報としてご利用ください。また、特定の施設や商品、サービスの利用を推奨するものではありません。
ひとりで悩んでしまう方は『絵本屋だっこ相談室』へご相談ください

絵本屋だっこでは、障害児ママたちが安心して相談できる場所をつくるため、また、障害児がいて外で働けないママたちの居場所をつくるため、『絵本屋だっこ相談室』を開設しました♪
ぜひお気軽に、ご相談にきてくださいね。
新米ママたちへ向けたお役立ち情報の掲載
こちらのコラムページでは、重心児や自閉症・発達障害などの障害児を育てる先輩ママたちにご協力いただき、新米ママたちへ向けたお役立ち情報を発信していきます!
<コラムに載せる内容例>
- 障害児ママたちの体験談まとめ【連載企画】
- 障害児向けの便利グッズ
- 障害児育児のお役立ち情報
- 障害児が使える福祉サービスについて
- 障害児の将来に関すること など……
今、子どもに障害を宣告され、不安いっぱいのママたち、まだまだ子どもが小さく先が見えず不安なママたちへ、必要な情報を届けられればと思っています。
コラム掲載のご案内は、公式LINEやインスタなどで行なっていきますので、ぜひチェックしにきてくださいね!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
▼絵本屋だっこInstagram

コラム記事を書いてみたい方を募集中!
絵本屋だっこでは、子どもに障害があって外に働きに出られないママたちの働き場所をつくる取り組みをスタートさせました。こちらのコラム記事執筆も、そのひとつです。
報酬は多くは出せませんが、お手伝いいただける方がいればぜひ公式LINEよりお問い合わせください。一緒に活躍の場をつくっていきましょう!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
ボランティアさんも募集中♪
絵本屋だっこコラムでは、障害児ママ以外にも、情報発信をしてくださる方を募集します♪
たとえば、特別支援学校の先生、リハビリの先生、デイのスタッフさんなど、障害児ママたちの不安を解消できるような情報発信をしたいという方がいましたら、ぜひご協力ください!
みなさまのあたたかなご協力をお待ちしております(^^♪