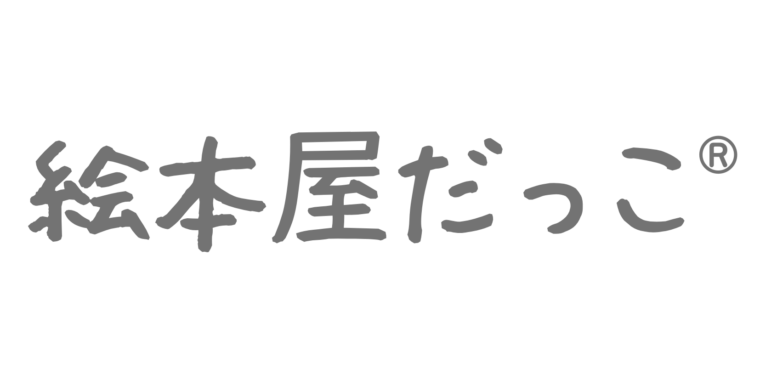こんにちは!絵本屋だっこコラム担当・相談室ピアサポーターのアイスです♪
ちょっとだけ自己紹介します。
【アイスってこんな人!】
- 寝ること・食べることが好きなアラフォー薬剤師
- 2人姉妹を育てており、次女が医療的ケア満載の重心児
- 福祉の支援やケアが必要な子の日常生活について、お母さん同士でおしゃべりしちゃう感覚でコラムを読んでもらえたら嬉しいです。
療育ってなに? わが家の療育ヒストリー|医ケア児ママの体験談
「療育って、いつから何を始めたらいいの?」
「この子に合う場所って、どう探すの?」
わが子が医療的ケアの必要な重症心身障害児(重心児)になったとき、たくさんの疑問や不安が押し寄せました。
これは、そんな私と娘が出会ってきた「療育」と「支援」の記録です。
どこかの誰かの「最初の一歩」の参考になれば嬉しいです。






1.はじめに:療育って、どんな場所?
娘が「療育」という言葉に初めて出会ったのは、生後半年ごろ。
先天性心疾患の娘は、生まれてすぐにNICUへ。生後半年までの間に2回の手術と複数回の検査入院。
長女と比べて発達の遅れがあったものの、入院生活で寝たままの状態で過ごす時間が長かったため、発達についてはあまり気にしていませんでした。
そんなわが家の療育へのきっかけは、かかりつけの総合病院の小児科で「発達を促すために、リハビリを受けてみませんか?」と医師(小児神経が専門の医師)から声をかけられたこと。
当時の私はその意味がよくわからず、「何か特別な訓練を受けさせるのかな」くらいの漠然としたイメージしか持っていませんでした。
療育=特別な支援という考えもなく、「この子に必要なことなら」と思って、月1~2回程度の通院リハビリに通い始めました。
2. はじめての療育:病院での個別リハビリから
生後半年頃、かかりつけの総合病院で「リハビリ」という名前の個別の療育が始まりました。
PT(理学療法士)さんとの関わりが中心で、不安定な体幹を支えたり、姿勢を整える練習などを遊びの中で取り入れてくれました。
リハビリ=がんばってやるもの・つらそうという先入観がありましたが、実際はとても穏やかで、「こんな姿勢でもいいんだよ」「こうやって声をかけてあげて」と、私たち親にも寄り添ってくれる時間でした。
その子に適したオーダーメイドの遊び方・関わり方を教えてくれました。
この頃から「子どもと一緒に学ぶ」という感覚が生まれた気がします。
3.療育園での集団療育:戸惑いと安心のなかで
娘の初めての集団生活となる療育園、今まで名称も存在も知らなかった施設への通所が始まりました。
3-1.療育園デビューは1歳すぎ
1歳を過ぎた頃、地域の児童発達支援センター、いわゆる「療育園」への通園が始まりました。
療育園とは、いわば「幼稚園+リハビリ」のような場所。
初めての親子通園で、月に数回、個別リハビリ(主にPT)と集団活動がありました。
集団活動では、同じクラスの子どもたちと一緒に歌を歌ったり、お絵かきをしたり、体を使った遊びをしたり、給食を食べたり。
体を使った遊びでは、抱っこや歩行の介助をしながら踊ったり、「今日は一緒にタオルブランコです!」など、まさにがっつり一緒に遊ぶスタイルでした。
当時の娘は肢体不自由があり、体幹も不安定な時期。
そして、常に酸素ボンベと一緒に行動する必要があるため、場所を移動するだけでも一苦労。
親が寝不足だったり体調が悪い日には「今日は休みたい…」と心が折れそうになることもありました。
3-2.療育園での数年間、リハビリと保育の両立
娘が2歳になるころには、理学療法(PT)に加えて、作業療法(OT)や言語聴覚療法(ST)も始まりました。
また、集団活動にも変化がありました。
クラスの人数も増え、動ける子と肢体不自由や医療的ケアがある子が混在しているクラスになりました。
そして、療育に通っているうちに、少しずつ娘に変化が見えてきました。
- 人との関わりを楽しめるようになったこと・
- 発語が少しずつ増えてきたこと
- リハビリを通して、体の機能がゆっくりでも確実に育ってきたこと
ゆっくりだけど、ちゃんと前に進んでいる。
そんな小さな「できた」が、私たち親子の心に光を灯してくれたんです。
3-3.医療的ケアが必要に。環境の変化と新たな選択
娘が3歳を過ぎたころ、心臓手術の後に低酸素脳症となり、気管切開・人工呼吸器・経鼻栄養などの複数の医療的ケアが必要な重症心身障害児(重心児)となりました。
重心児の中でも娘の症状は重く、常に医学的管理下に置かなければ、呼吸をすることも栄養を摂ることも困難な障害状態(超重症児)と呼ばれる状態です。
そのため、家に帰るまでの準備期間となる1年間の入院生活を経て、在宅移行が決まったころ、新たに「重心児向けのデイサービス」を契約することにしました。
このデイは、児童発達支援と放課後等デイサービスが併設された施設。医療的ケアにも対応していて、送迎もあり。
幸運にも、娘の長期入院中にデイができたという話をママ友から聞いていたため、在宅に戻る話が出た段階で見学に行き、契約をしました。
3-4.療育園とデイのダブル利用へ
在宅に戻ってからも、これまで通っていた療育園には週1回親子で通園することに。
正直、療育園の母子通園はしんどい時期もありました。
私が通っていた療育園は、元々は発達障害児向けの施設です。
当時は看護師が常駐しておらず、子どもの介助や医療的ケアなどはすべて付き添いの母親任せ。
私たちの地域は、療育の選択肢がとても少なくて…
肢体不自由のある子や重症心身障害児、医療的ケアが必要な子どもたちを受け入れてくれる場所がほとんどありませんでした。
そんななか、療育園が引き受けてくれて本当にありがたかったのですが、そこで用意されていたプログラムは「動ける子」が基準になっていることも多く、首も腰も座らなくなってしまったわが子にとっては難しい場面も…
復帰した最初は「うちの子、ここにいていいのかな」と戸惑うこともありました。
娘が寝たきりの医療的ケア児になってからは、自由に体を動かしていた以前の娘を思い出して自然と涙がでてくることもありました。
どうしても精神的にしんどくなった時期は、通園日数を減らしたりして、親子共に無理なく通うスタイルにしました。
それでも、先生方は一人ひとりの発達や体調をきちんと見てくれて、子どもの可能性を信じて、できることを少しずつ広げてくれました。
「一般的な発達ではなくても、この子にはこの子の楽しみ方がある」
そう思えるようになったのは、この療育園での経験があったからです。
3-5.支えてくれたのは、同じ道を歩くママたち
いろんな障害や特性をもつ子どもたちが通っていた療育園だからこそ、
「みんなちがって、それぞれに良さがある。
みんなちがって、それぞれに大変なこともある」
そんなことを、頭ではなく心で感じられた時間だったように思います。
とても貴重で、大切な経験でした。
また、療育園では、肢体不自由児のクラスはずっとメンバーが変わらなかったため、自然とママ同士が仲良くなりました。
年齢の違う先輩ママ・後輩ママとの縦の繋がりが深まったのも、母子通園ならではのメリットです。
それぞれの立場や背景は違っても、「ケアが必要な子を育てている」その経験だけは、みんなが分かち合えるものでした。
障害の内容や医療的ケアの種類は違っても、誰にも話せなかった悩みや不安を「わかるよ」と受け止めてくれる人がいる、それだけで心がふっと軽くなったのを覚えています。
当事者のママたちだからこそわかり合えることがあり、どんなに励まされたか分かりません。
卒園してからも、その繋がりは続いています。学校やデイサービスの情報交換をしたり、ときどきランチに行ったり。
「この子に合うデイはどこだろう?」
「ここの学校、こうだったよ」
そんなリアルな声が聞ける場所があるのは、本当に心強いです。
療育で一番助かったのは、実は、私の気持ちを受けとめてくれる人がいたことかもしれません。
「ひとりでがんばらなくていい」
そう思えたことで、子どもを見る目にも少し余裕が出てきた気がします。
4. 放課後等デイサービス:親のレスパイトも大切に
小学校入学後、地域に医療的ケア児も受け入れてくれる放課後等デイサービスが新たにできたことで、2箇所の通所をスタートしました。
平日、学校から直接送迎してくれるのは本当にありがたく、子どもにとっても家以外の居場所が増えたことが嬉しかったようです。
デイでは、制作活動や季節の行事、ちょっとした外出など、学校とは違う経験を重ねていました。
スタッフには看護師やリハビリ職の方もいて、安心して預けられる環境が整っていました。
娘のデイでは、入浴支援もあったため、帰宅後にいつもよりゆっくりと過ごせるのもありがたいです。
そして何よりも大きかったのが、親がホッとできる時間が持てるようになったこと。
ほんの数時間でも、心と体を休めることができると、子どもにも穏やかに向き合える自分になれるのです。
5. 療育のかたちは一つじゃない:振り返って思うこと
今振り返ると、わが家は「いろんな療育を体験できてよかったな」と感じています。
現在通っている2ヶ所のデイサービスは、それぞれに違った魅力があります。
ひとつは、保育の要素が強くて、体をたくさん動かして過ごすアクティブなデイ。
もうひとつは、その日の体調に合わせて、ゆったり穏やかに過ごせるデイ。
うちの娘は体力がないので、毎日アクティブなデイだと疲れすぎて体調を崩してしまいます。
でも、ゆっくり過ごすだけでは刺激が少なく、できることを伸ばすチャンスが減ってしまうかもしれません。
だからこそ、それぞれ違った「カラー」を持つデイを使い分けることで、娘にとって無理のない、ちょうどいいバランスで過ごせているんだなと感じています。
子どもの体調や性格に合わせて、その子にとってちょうどいい環境を探すことって、本当に大切なんだなと実感しています。
完璧な場所じゃなくても、いくつかの選択肢を組み合わせることで、その子らしく安心して過ごせる毎日がつくれるんだと思います。
合う・合わないは、やってみないと分からない。
その時は「合わないかも」と思った場所も、子どもの成長や環境の変化によって、また新たな価値が見えてきたりします。
療育の本当の目的って、「この子に合った関わり方を見つけること」なんじゃないかなと、今は思っています。
無理に何かを伸ばすよりも、この子らしさを尊重しながら過ごせる場所を見つけていく過程こそが、大切な意味を持つんだと気づかされました。
6.療育のカタチは家庭ごとにちがう
低酸素脳症になった時は、脳障害があるのに、療育をする意味があるのかなと何回も何回も考えました。
療育を始めるタイミングも、選ぶ施設も、子どもや家庭の状況によってさまざまです。
地域によって選択肢が少ないこともあるし、親の体調や生活スタイルによって通い方も変わってきます。
でも、どんな道を選んでも、「この子のためにできることをしたい」と思うママの気持ちは、きっとどこかでちゃんと届いているはず。
療育って、正解があるようでない世界。
だからこそ「うちのペースで、うちの子に合ったやり方で」進めばいい。
そう今は思っています。
はじめの一歩は、誰だって不安です。
でも、どんな療育も、子どもや家族の成長のきっかけをくれる場所だと思います。
今振り返ると、「このとき、こうすればよかったのかな」と思うこともあります。
でも、あのときの自分が選んだことは、その時できる最善だったと、今では思えます。
今、子どもが笑って過ごしている姿を見ると、それだけで満点としています。
同じように迷いながら、日々を懸命に生きるママたちへ。
「大丈夫、一人じゃないよ」と、少しでも届けば嬉しいです。
7.おわりに
もし、今ちょっと療育で悩んでいるママがいたら、ひとつだけ伝えたいことがあります。
あなたは、もう十分がんばっています。
「同じような経験をしている人がいる」と知るだけで、少し心が軽くなることもあります。
わが家の体験が、誰かのヒントになりますように。
療育には、正解もひとつのかたちもありません。
まわりと比べず、「今のわが家に合っているかどうか」を大切にしていきたいですね。
ひとりで抱え込まずに、少しずつでも安心できる道を一緒に見つけていきましょう。
「うちはこれでいいのかな?」と迷うこともあるかもしれませんが、必要な支援を柔軟に選んでいけたら、それが一番だと思います。
どんなかたちでも、お子さんとご家族が無理なく続けられることが、いちばん大切です。
お子さんのペースも、ご家族のペースも、大切にしながら進んでいけますように。
このコラムが、これから療育の一歩を踏み出そうとしている方の背中を、そっと押せる存在になれば嬉しいです。
そして、療育の先に見据えているのは、「わが子なりの自立」です。
「自立」と聞くと、一般的には自分の力で生活していくことや仕事をして自活することを思い浮かべるかもしれません。
でも、娘のように医療的ケアが必要な重心児にとっては、その意味が少しちがってきます。
わが家が目指している「自立」は、
「どこにいても、誰のサポートを受けても、安定して安心して過ごせること」
そして、困ったときに「助けて」と伝えられること、必要な支援につながる力を育てることと、という風に考えています。
娘が大人になるまでの時間、
少しずつ、でも確実に「娘なりの自立」に近づけるように。
これからも、親子で一緒に歩んでいけたらと思っています。
*絵本屋だっこのコラムに関しては、全ての方に当てはまる情報ではございません。
投稿された情報の利用により生じた損害については、絵本屋だっこでは責任を負いかねます。あくまでもご家庭での判断のもと参考情報としてご利用ください。また、特定の施設や商品、サービスの利用を推奨するものではありません。
ひとりで悩んでしまう方は『絵本屋だっこ相談室』へご相談ください


絵本屋だっこでは、障害児ママたちが安心して相談できる場所をつくるため、また、障害児がいて外で働けないママたちの居場所をつくるため、『絵本屋だっこ相談室』を開設しました♪
ぜひお気軽に、ご相談にきてくださいね。
新米ママたちへ向けたお役立ち情報の掲載
こちらのコラムページでは、重心児や自閉症・発達障害などの障害児を育てる先輩ママたちにご協力いただき、新米ママたちへ向けたお役立ち情報を発信していきます!
<コラムに載せる内容例>
- 障害児ママたちの体験談まとめ【連載企画】
- 障害児向けの便利グッズ
- 障害児育児のお役立ち情報
- 障害児が使える福祉サービスについて
- 障害児の将来に関すること など……
今、子どもに障害を宣告され、不安いっぱいのママたち、まだまだ子どもが小さく先が見えず不安なママたちへ、必要な情報を届けられればと思っています。
コラム掲載のご案内は、公式LINEやインスタなどで行なっていきますので、ぜひチェックしにきてくださいね!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
▼絵本屋だっこInstagram


コラム記事を書いてみたい方を募集中!
絵本屋だっこでは、子どもに障害があって外に働きに出られないママたちの働き場所をつくる取り組みをスタートさせました。こちらのコラム記事執筆も、そのひとつです。
報酬は多くは出せませんが、お手伝いいただける方がいればぜひ公式LINEよりお問い合わせください。一緒に活躍の場をつくっていきましょう!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
ボランティアさんも募集中♪
絵本屋だっこコラムでは、障害児ママ以外にも、情報発信をしてくださる方を募集します♪
たとえば、特別支援学校の先生、リハビリの先生、デイのスタッフさんなど、障害児ママたちの不安を解消できるような情報発信をしたいという方がいましたら、ぜひご協力ください!
みなさまのあたたかなご協力をお待ちしております(^^♪