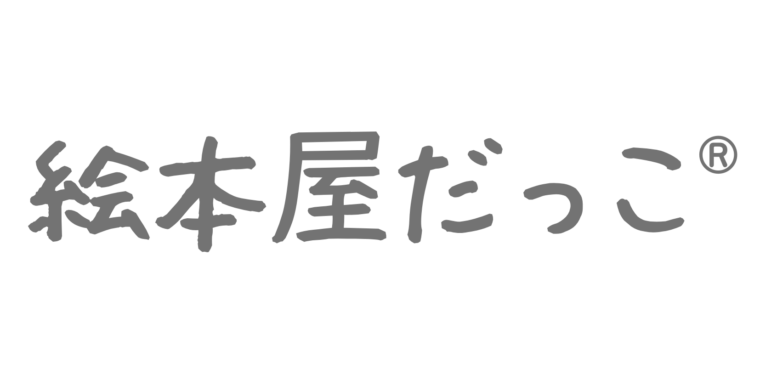こんにちは!絵本屋だっこコラム担当・相談室ピアサポーターのアイスです♪
ちょっとだけ自己紹介します。
【アイスってこんな人!】
- 寝ること・食べることが好きなアラフォー薬剤師
- 2人姉妹を育てており、次女が医療的ケア満載の重心児
- 福祉の支援やケアが必要な子の日常生活について、お母さん同士でおしゃべりしちゃう感覚でコラムを読んでもらえたら嬉しいです。
- 資格・肩書
・心理カウンセラー
・睡眠コンサルタント
・絵本屋だっこピアサポーター
・NPO法人絵本屋だっこ副理事
・心理カウンセラーは、専門知識をもとに、クライアントが抱える悩みや心の問題について支援を行う専門家です。
・睡眠コンサルタントは、睡眠の質や習慣を改善するためのアドバイスやサポートを提供する専門家です。

睡眠の質を上げるポイント(気持ち良く眠りにつく方法)を体験談を交えて解説!!
暦の上では春になっているにも関わらず、冬のような寒さの日が定期的にやってきますね。
春は明るいイメージがありますが、寒暖差や気圧変動が大きいため、自律神経が乱れやすく、心や体がソワソワしやすい時季です。

そのため、普段からメンタル面などで不調のある人は悪化しやすく、また特に不調がない人でも、大きなストレスが加わると不調に陥りやすいとされています。
まさに今、心身共に要注意のシーズンですね。
春休み前後から目に見えない気圧の変動の影響を受けて、何故か頭痛がしたり、異様に疲れやすくなったり、眠たくなったり、肩がこりやすくなったりと、細かい異変が出てきている方もいるのではないでしょうか?
これらの症状は、大人や環境の変化に敏感な子ども、寝たきりの子どもが特に感じやすいとも言われています。

最近は、天気予報や気圧の変化を気圧グラフとして目に見えるようにした「頭痛ーる」などのアプリもあります。
原因不明のだるさや眠気などが続く際には、アプリなどで健康の記録をつけると自身の傾向が分かるかもしれません。
そして、特に心身にダイレクトに影響を与えるのが、睡眠問題。
「春眠暁を覚えず」という言葉を聞いたことがある方も多いかと思いますが、春は眠気がちで、朝起きられないといった症状に悩む方も少なくありません。
こちらの原因としては、寒暖差によるもの、忙しさのために夜間の睡眠時間が不足しがちになることなどの環境要因の他に、体の生理的な問題も関わってることが明らかになってきています。

眠気を誘発するホルモン(メラトニン)の分泌や自律神経のリズムが冬から春にかけて大きく変化することが、睡眠にも影響を及ぼしているといわれています。
眠くなったり、寝つきが悪くなったりと、質が下がりがちな春の睡眠。
そこで、今回は、前回の知恵袋(睡眠環境の整え方)と合わせて活用できる睡眠の質について、より深く切り込んでいきたいと思います。

忙しい毎日の中でも実践しやすいちょっとした工夫、
親子一緒にぜひ一度お試しくださいね。
1 意識したいホルモンと神経のひみつ
睡眠と深く関係する、ホルモンと神経の関連から、寝つきをよくする方法について解説します。
①睡眠ホルモン(メラトニン)を出す方法
メラトニンの分泌を促す対策としては、主に下記の方法が有効と言われています。
- ・起床後2時間以内に太陽の光を浴びる(窓際での日光浴でも有効)
- ・寝る前には、自分がリラックスする香りを取り入れる(ラベンダー、ベルガモット、カモミール、ヒノキ、オレンジなど)
- ・思い切って昼寝の時間を作る(15時までに、20分以内の昼寝が望ましい)
- ・布団や枕のカバーを見直す(季節に応じた快適さを感じる物に変えてみる)
②よく聞く自律神経の乱れとは?
自律神経が乱れると睡眠の質が下がるといわれますが、その仕組みについて解説します。


自律神経とは、自分の意思とは関係なく自動的に働く神経です。
生命維持に必要な機能を調節するために、24時間働き続けています。
具体的には、交感神経(体を活発に動かす時に働く、興奮系の神経)と副交感神経(体を休める時に働く、鎮静系の神経)があり、通常はこの2つの神経が絶妙なバランスを保つことで、私たちの体の機能を調整してくれています。
この2つの神経のバランスが崩れてしまうと、心身共に様々な不調が現れます。
特に多いものとして、以下の症状があります。
- めまい
- 頭痛
- のぼせ
- 疲れ、だるさ(倦怠感)
- 肩こり
- 腰痛
- 不眠(昼間眠い、目覚めが悪い)
- 不安、うつ(憂鬱な気持ちになる)
- イライラする(神経質になる)
意外と身体面の不調も多いことが分かるかと思います。
③自律神経を整えよう!
自律神経を整えるためには、以下のような習慣が有効といわれています。
- 規則正しい生活習慣(毎日の落ち着くルーチン)を心がける
- ストレス管理に気をつけ、リラックスできる時間を取り入れる
- 栄養素をなるべく食事から積極的に摂る(ビタミンB1、カルシウム、ミネラルなど)
- ゆっくり&長くできる運動をする(ウォーキング、軽めのランニングなど)
- 意識して深呼吸をする
- 体温調節ができる服装を心掛ける
2 パジャマの効果
ここまでは、春に限らず、1年を通して実践できることをあげてきました。
さて、ここからはより就寝時に特化した情報になります。
春の不調を改善するヒントになれば、嬉しいです。
パジャマで睡眠の質が上がる!?


みなさんは、就寝時の服装にこだわりがありますか?
実は、パジャマを着ることで、睡眠の質を上げることができます。
パジャマは、寝るときに着ることを考えて作られているだけあって、着心地には部屋着(ルームウェア、ラウンジウェアなど)と雲泥の差があります。
吸湿性に優れ、肌に優しく、身体を締め付けないように作られている物が多く、リラックスして眠りにつきたい時に最適です。
パジャマは素材選びが大切
パジャマの素材は、以下のようなポイントで選ぶのがおすすめです。
- 肌ざわりがいいもの
- 摩擦が少ないもの
- 寝返りを打ちやすいもの
シルクのように肌触りの良い生地は、着ているだけで副交感神経を活発にしてくれます。
また、スムースニットやダブルガーゼといった生地で作られたパジャマは摩擦が少ないので、部屋着と違って小さな力で寝返りが打てます。
パジャマの素材選びが大切な理由
寝返りの回数が必要以上に増えると、せっかく睡眠が持っている疲労解消の効果が妨げられてしまいます。
そのため、摩擦が少ない生地のパジャマを選ぶことで、小さな力で寝返りが打てるため、寝ている時の疲労も少なくしてくれます。
着慣れた部屋着も楽ですが、ベッドの中で着ることを考えて作られていないので、あまり汗を吸わず、体温調節がしにくい場合があります。
3 冷えの解消は「楽」を意識して
睡眠の質を上げるためには、冷えを防ぐ工夫も大切です。


「冷え」には、自覚できるものと無自覚のものがありますが、睡眠の質を下げる原因になるため対処が必要です。
身体が冷えていると、トイレに起きる回数が増えたり、充分な睡眠時間をとっているにも関わらず、疲れが解消されにくくなったりします。
また、手足の先端が冷えていると、身体の深部体温が下がらないので、眠りが浅くなってしまうといわれています。
冷えを対処し眠りの質を上げるポイントをご紹介します。
身体の締め付けをなくす
冷えを解消するには、まず第一に、身体の締め付けをなくすことが大切です。
具体的には、下着はつけないことがオススメです。
下着をつけていないと不安な方は、おやすみ用の下着(締め付けが少ないもの)や腹巻きを着用して寝ることにより、身体の締め付けが減って血行が良くなるので、手足が冷えるのを防ぐことができます。
締め付けが減るだけで、身体への負担も軽くなります。
アイスのおすすめ対策
個人的に、効果抜群だと感じたのは、睡眠用のレッグウォーマー、アームウォーマーを併用することです。
冷えを自覚する前に、ぜひお試しください。
寝るときに身につけるもので冷え対策を
このように、ほんの少し身につけるものを工夫することで、眠りの質は良くすることができます。
子育ての中での貴重な睡眠時間、どうせ眠るのなら、少しでも気持ち良く眠りたいですよね。
睡眠が心地良いものになれば、眠りにつくこと自体がひとつの楽しみになり、日中の生活にもハリが出てくるかもしれません。
すぐにできる睡眠改善方法なので、親子一緒にぜひお試しくださいね。
4 寝具の選び方


寝具を選ぶ基本は、普段立っているときの自然な姿勢をそのまま就寝時にも保てるようにすることです。
快適な睡眠のためにこだわってみてほしい寝具は、主に下記の3つです。
- 枕
- マットレス
- 布団
それぞれの選び方・睡眠の質を上げるポイントをご紹介します。
①枕


枕は、高め・低め、硬め・柔らかめなどの個人の好みがよく反映されるアイテムです。
起床時の首や肩の疲労感を感じた時には、見直しをしてみるタイミングかもしれません。
身体に合った枕の高さは意外と低いものです。
高い枕は、首のシワ、二重あご、いびきの原因にもなるため、漫然と同じ枕を使い続けているのは危険かもしれません。
②マットレス


睡眠が持っている疲労解消の効果を存分に発揮できるのが、マットレスです。
特に、寝たきりの子どもと一緒に使う場合、体の発育(骨や筋肉)に大きく影響を与えるものとして私は考えています。
重要なのは、体圧分散性(マットレスからの圧力を全身に均等に分散すること)。
睡眠中の動きが少ない人や睡眠時間が少ない人には低反発のもの、
頻繁に寝返りを打つ人には高反発のものが向いているといわれています。
好みもありますので、「気持ち良く熟睡できているか」をマットレスとの相性の診断に使ってみてください。
自分に合ったマットレスだと、起床時の全身の軽さに驚きます。
介護用マットレスなども市販されているので、長く使えるものを選べたらうれしいですね。
③掛け布団


掛け布団は、自分が快適と感じるものを選ぶこと、季節に応じて何パターンか組み合わせを持っておくと安心です。
体に触れる面積が大きいものなので、通信販売は避けて、お店に行って自分の手で品質を確かめてからの購入がオススメです。
毎日使うものですから、きちんと納得のいくものを選ぶことが、寝る楽しみにつながります。
心地よい寝具で睡眠の質をアップ
このように、着るものや寝具を見直したら、次は寝室を見直してみるのもオススメです。
部屋が、自分にとってリラックスできる、心地の良い空間になっていれば、自然と眠りの質も向上します。
思い切って、部屋全体の模様替えをするのも楽しいものですが、ここでは、もう少し手軽に寝室の居心地を良くする方法も考えてみましょう。
5 快適な寝室づくり


みなさん、寝室の状態はいかがでしょうか?
ケアがある子の場合、医療的ケアで使う機械や物品で部屋の空間が圧迫されやすかったり、子どもと同室で寝る必要がある場合には寝具がかさばったりして、部屋全体がごちゃついてしまうといった様子はないですか?
うちは、寝室兼子ども部屋で24時間の医療的ケアが必要な子どもとそのきょうだいと一緒の寝室のため、スッキリした空間作りにはいつも苦戦をしています。
実は、睡眠の質の問題には部屋の状態も関わっていると知り、意識して部屋を整えようと気をつけるようになりました。
ここでは、快適な寝室づくりのポイントをご紹介します。
①片付ける


まず、部屋を片付けるだけでも睡眠の質は向上するといわれています。
多少散らかっていても、毎日のことだと慣れてしまいがちです。
しかし、「部屋の状態は、その人の心の中が反映されている」という言葉があるように、いつもより散らかっているなと自覚する部屋で過ごしていると、なぜか落ち着かない気持ちになることはありませんか?
その理由として、単純に片付いた様子は気持ちが良いものです。
そして、そこに至るまでの少しの満足感や達成感が心をほぐしてくれるようです。
また、散らかった部屋にはホコリや湿気が付きものです。
健康面からも、ある程度は整理された空間になるように部屋を片付けることが、快適なリラックス空間につながり、プチストレスの軽減にもなります。
片付けにより勝手に目に飛び込んできていた視覚的情報を整理することで、知らず知らずのうちに使っていた情報の受け取りも減らせた結果、リラックスしやすくなるというメリットもあります。
ベッドと壁を離すレイアウトも、通気性が良くなり、快適な環境づくりにつながります。
②癒しのカラーに注目
部屋がスッキリした後は、インテリアについても考えてみませんか?


気分が上がる明るいカラーを使ったお部屋づくりも素敵ですが、寝室に関していうと、あまりオススメできません。
理由として、色彩は、人の心理に大きな影響を与えるためです。
原色を見れば気持ちが興奮し、自然のなかにある色みを見ると気持ちが落ち着きます。
やすらぎや安心感を与えてくれたり、リラックス効果があるのは、ベージュ、パステルカラー、淡いブルーやグリーンという研究結果があります。
壁紙や家具の色彩に統一感がなかったり、派手な原色などの強い色彩のものが多い状態では、自分で意識していなくても、目から飛び込んだ色彩が脳を興奮させてしまい、快適な睡眠環境の妨害してしまう可能性があります。
③光のバランス
次に、夜間の照明は光のバランスに注意してみましょう。
豆電球をつけたまま寝る人、真っ暗な状態にしないと寝付けない人、うちみたいに人工呼吸器やサチュレーションモニターの明かりで寝る人など、照明に関してはそれぞれの環境と理由があると思います。
そのなかでも、できる工夫で光のバランスを整えることで、睡眠の質を高めることができます。


夜間の照明によりホルモンバランスが変わる
睡眠中の部屋の明るさについて、興味深い研究があります。
蛍光灯の豆電球をつけて眠る人は、灯りをすべて消した真っ暗な状態で眠る人よりも中性脂肪が多く、また肥満にもなりやすいとのことです。
理由としては、豆電球程度のごくわずかな光といえども、一晩中浴びていることで、メラトニンの分泌が抑制されて、食欲を増進させるホルモンの分泌が増進されるためと考えられています。
私には、とても思いあたるふしがある結果でした。
とはいっても、真っ暗な部屋で眠るのは難しいので、いろいろな機械の光源の位置を目に入らない場所に移動させてみたりと、少しでも光の影響を減らそうとしています。
明かりをベッドの死角に置くだけでも、違いがあるようです。
眠っていても光の影響を受ける
人は、目を閉じた状態でも、瞼を通して目の中にある網膜が光をキャッチしているそうです。
夜が明けるにしたがって、ゆっくりと部屋の中も明るくなるような環境だと、体内時計もリセットされ、すっきり目覚めることができます。
遮光カーテンなどを取り入れて部屋の明るさを調節してみるのも、快適な睡眠環境につながりそうです。
④香りの力でリラックス
さて、最後の部屋づくりに、目に見えない香りのパワーを借りてみませんか?


寝室に香りを取り入れるおすすめアイテム
色彩と同じように、香りも人の心に影響を与えます。
アロマディフューザーやアロマストーンを使えば、火を使わないため、安心して香りを楽しみながら眠ることができます。
また、アロマ加湿器を使えば、冬場の乾燥を防ぐこともできます。
ただ、ダイレクトに香りが室内に充満するので、家族と一緒の寝室だと使いづらい方もいらっしゃるかと思います。
そこで、アロマ検定1級保持者の私のオススメは、あらかじめ複数の香りがブレンドされたアロマミスト(ルームミスト、フレグランスミストなど名称多数あり)です。
また、生活の木など本格的なアロマのお店の香りはきついと感じる場合は、無印良品で販売されているようなフレグランスミスト(ルームスプレー)ならトライしやすいと思います。
気分やシチュエーションに合わせて香りを選べるようになっているので、ぜひ購入前に実際の香りを試してみて、今の自分に合った香りを選んでみてくださいね。
リラックスできる香りで睡眠の質をアップ
香りの好みは千差万別です。
好みに合わない香りはむしろ苦痛になりますので、一般的なリラックス効果のある香りにとらわれず(例えば、安眠効果にはラベンダーの香りなど)、その日の気分や体調、なりたいイメージに合わせて、香りをチョイスしてみてくださいね。
香りの力は、子どもにも使いやすいです。
ただ、子どもの空間からは、大人に使うときよりも少し離れたところに香りを置くようにするようにだけご注意ください。
6 体を温めると、睡眠の質がアップするひみつ
次に、体温と睡眠の関係と、睡眠の質アップのポイントをご紹介します。


湯船に浸かって入浴すると、心も体もじんわりとほぐれていく感じがしませんか?
これは、入浴によるリラックス効果だけでなく、生理的な理由もあります。
入浴は、主に3つの効果(温熱効果・水圧効果・浮力効果)が得られます。
特に、入浴するお湯の温度は、身体への影響も大きいところです。
①入眠しやすいお風呂の温度とは?
眠りにつながるお湯の温度について解説します。
おすすめはぬるめのお湯に15分
38〜40℃前後のぬるめのお湯(副交感神経が働く)は、緊張がほぐれてリラックスした気分になります。
ぬるめのお湯にゆっくり15分ほどつかることで、身体の深部体温をしっかり上げることができます。
1日の疲れを取りたいときや、くつろぎたい時に適した入浴スタイルです。
保温効果のある入浴剤もオススメです。
高温は交感神経が活発になる
一方、42℃を超えるような熱いお湯(交感神経が働く)は、心身ともに活発になります。朝など眠気を覚ましたいときや、これからもうひとがんばりしたいというときに適したスタイルです。
熱めのお風呂に入ることでスッキリした気分になるかと思います。
ただし、熱いお湯は体力を消耗してしまうので、長湯は禁物です。
冷え性の人は熱めがおすすめ
実は、冷え性の人は、熱めのお湯(42℃程度)に15分がオススメと言われています。
ぬるめのお湯にゆっくり入っても、寒さが続いていることはないですか?
冷え性の人は深部体温が温まりにくく下がりにくいため、一般的な入浴スタイル(38℃のお湯に15分)だと身体の芯まで温めることができません。
その結果、しっかりと睡眠をとったにも関わらず、疲労感がとれない場合もあります。
②お風呂に入るタイミング
人間は、体温が下がるタイミングで眠くなると知られています。
体温が下がるタイミングで眠くなる
入浴後は一時的に体温が上がるため交感神経が働き、徐々に体温が下がるタイミングで副交感神経が優位になり、眠くなります。
入浴してから体温が下がるまでは、2~3時間といわれます。
そのため、就寝時間の2~3時間ぐらい前に入浴し、しっかり汗を流すようにして、眠くなる体温のリズムにあわせましょう。
そのため、就寝時間の最低1時間前(1〜3時間前が望ましい)には入浴し、いったん体温を上げておくことで、体温が下がるタイミングでスムーズに入眠できます。
③入浴できない時は、手と足を温めて
お風呂に入る気力もないほど疲れた時や、生理でお風呂に入りたくない時でも、手や足だけでも温めてあげると、熟睡できて疲労の回復も早くなるといわれています。
看護の現場でも、手浴・足浴を取り入れているところが多い実戦的な方法です。
具体的には、熱めのお湯(42℃程度)を洗面器に入れ、手足を10分程度温めてみましょう。
手だけなら、洗面所のシンクにお湯を張るだけで簡単にできます。
疲れているときこそ、身体をいたわって、快適な睡眠をとれるように心がけてみると、翌日以降に疲労の持ち越しが軽減されると思います。
7 おわりに
子育て中は、決められたスケジュールをこなすことでいっぱいいっぱいになることも多いと思います。
限られた時間の中で、いかに睡眠の質を高めることができるのか。
すぐに試してみることができる方法もコラムに載せたので、1つでもみなさんの参考になることがありましたらうれしいです。
春は親子ともに新しい環境になることが多いと思いますが、新たな活動やルールが増えると、自覚がないままに緊張や疲労が蓄積されやすくなるため、無理のない範囲で生活リズムを見直してみるのもオススメです。
今回のコラム、親子で使えるセルフケアとしてぜひお試しくださいね。
8 今回のおすすめの本
最後に、親子で一緒に睡眠導入ができるおすすめの絵本をご紹介します♪
■可愛く癒される絵本
・おやすみくまちゃん
なかなかベッドに入ろうとしない、眠ろうとしないで遊ぶくまちゃんたち。
子育て中のママなら、自分の子どもと同じだな〜と思わず苦笑してしまうほどのリアルが可愛いイラストで描かれています。
絵を眺めているだけで、ほんわかと癒されます。
こちらのくまちゃん、シリーズで出版されています。
■ベッドタイムに読んでほしい、優しい絵と文の心やすらぐ絵本
・おやみなさいのほん(世界傑作絵本シリーズ)
私が子どもの頃からの、我が家での寝かしつけ絵本。
大人になってから手に取っても、心が落ち着きます。
まるで地上から離れた高いところにいる神様に見守られながら眠りにつくような、不思議な絵本です。
■リズミカルな言葉選びが睡眠を誘う絵本
・ねないこだれだ (いやだいやだの絵本)
赤ちゃん向けかと思いきや、大人が読んでも少し怖い絵本。
一見可愛らしい見た目のお化けですが、寝ない子を見つけると…
ストーリー性抜群、子どもが怯える寝かしつけの絵本。
ひとりで悩んでしまう方は『絵本屋だっこ相談室』へご相談ください


絵本屋だっこでは、障害児ママたちが安心して相談できる場所をつくるため、また、障害児がいて外で働けないママたちの居場所をつくるため、『絵本屋だっこ相談室』を開設しました♪
ぜひお気軽に、ご相談にきてくださいね。
新米ママたちへ向けたお役立ち情報の掲載
こちらのコラムページでは、重心児や自閉症・発達障害などの障害児を育てる先輩ママたちにご協力いただき、新米ママたちへ向けたお役立ち情報を発信していきます!
<コラムに載せる内容例>
- 障害児ママたちの体験談まとめ【連載企画】
- 障害児向けの便利グッズ
- 障害児育児のお役立ち情報
- 障害児が使える福祉サービスについて
- 障害児の将来に関すること など……
今、子どもに障害を宣告され、不安いっぱいのママたち、まだまだ子どもが小さく先が見えず不安なママたちへ、必要な情報を届けられればと思っています。
コラム掲載のご案内は、公式LINEやインスタなどで行なっていきますので、ぜひチェックしにきてくださいね!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
▼絵本屋だっこInstagram


コラム記事を書いてみたい方を募集中!
絵本屋だっこでは、子どもに障害があって外に働きに出られないママたちの働き場所をつくる取り組みをスタートさせました。こちらのコラム記事執筆も、そのひとつです。
報酬は多くは出せませんが、お手伝いいただける方がいればぜひ公式LINEよりお問い合わせください。一緒に活躍の場をつくっていきましょう!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
ボランティアさんも募集中♪
絵本屋だっこコラムでは、障害児ママ以外にも、情報発信をしてくださる方を募集します♪
たとえば、特別支援学校の先生、リハビリの先生、デイのスタッフさんなど、障害児ママたちの不安を解消できるような情報発信をしたいという方がいましたら、ぜひご協力ください!
みなさまのあたたかなご協力をお待ちしております(^^♪