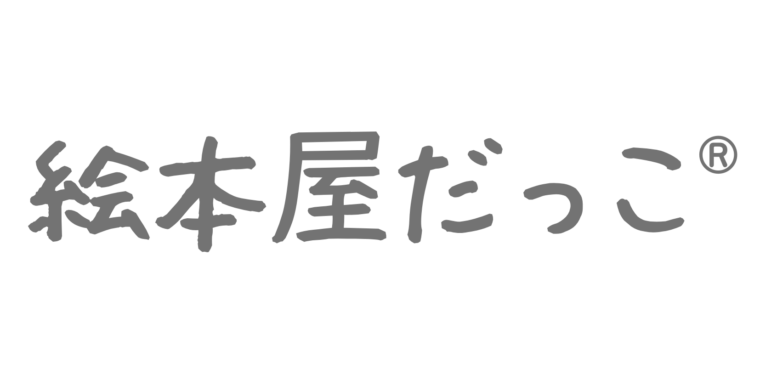こんにちは!絵本屋だっこコラム担当・相談室ピアサポーターのアイスです♪
ちょっとだけ自己紹介します。
【アイスってこんな人!】
- 寝ること・食べることが好きなアラフォー薬剤師
- 2人姉妹を育てており、次女が医療的ケア満載の重心児
- 福祉の支援やケアが必要な子の日常生活について、お母さん同士でおしゃべりしちゃう感覚でコラムを読んでもらえたら嬉しいです。

障害がある子の清拭(体を拭くケア)のポイントとは? 医ケア児ママが体験談を交えて解説!!
医療的ケア児、肢体不自由児など介助が必要な子の入浴方法について、先日の体験談やコラムでまとめてみました。
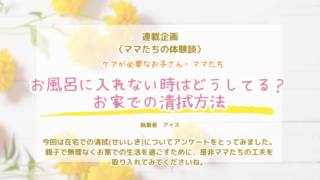



みなさんの体験談を聞くと、家族が中心となっておうちでの入浴を行なっているケースが多かったですが、入浴やシャワーが難しい場合のケアについて、何をどこまでどうしたらいいのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
通院後などの親子そろって疲れはてている時、体調をくずしている時、
ケガなどで体を動かしづらい時、
おうちでゆっくりと過ごしたい時、
清潔を保つ方法として、清拭(せいしき)があります。
清拭とは、子どもの肌の健康を保ち、快適さを提供するための重要なケアになります。
そこで、今回の記事では、看護・介護の場でも役に立つ清拭(主にベッド上で体を拭くケア)について、体験談を交えながら詳しく紹介していきます。
記事の最後の方に、時短にもなる便利グッズを使ったやり方も取り上げているので、ワンオペが多いママさんにぜひ読んでみてほしいです。
1.清拭(せいしき)とは?


清拭とは、身体を清潔に保つために、濡れたタオルや蒸しタオルなどで体を拭くことを指します。
入浴が難しい人(高齢者、医療的ケア児や肢体不自由児)、病気やけがなどで入浴やシャワー浴ができない場合に行われます。
椅子などに座った姿勢で行ったり、ベッド上で寝た姿勢で行ったり、個人の体の状態に合わせて行うことができるケアになります。
また、皮膚状態や体調変化をゆっくりと把握する機会でもあります。
2.清拭の目的
清拭には、主に5つの目的があります。
①清潔の保持
汗や皮脂、汚れを除去し、皮膚を清潔に保ちます。
②感染予防
皮膚の汚れを取り除くことで、細菌やウイルスの増殖を防ぎ、感染症を予防します。
③血行や循環を良くする
温かいタオルで拭くことで、血行が良くなり、体温調節や新陳代謝を促進します。
④リラクゼーション効果
温かいタオルで拭くことで、心身がリラックスし、精神的な安定を促します。
⑤褥瘡(じょくそう)予防
皮膚を清潔にすることで、床ずれ(褥瘡)のリスクを減らします。
3.清拭の種類


清拭の種類として、2つの方法があります。
- 全身清拭:全身を拭く方法
- 部分清拭:顔や手足、背中など、必要な部分のみを拭く方法
清拭を行う時の体調・時間のゆとりの有無などから、短時間でケアを終わらせたい時は、汗をかきやすい場所を中心に、部分清拭を行うのがおすすめです。
汗をかきやすい場所は、汗腺(特にエクリン汗腺)が多く分布している部位や、体温調節のために発汗しやすい部位です。
主な汗をかきやすい部位としては、下記があげられます。
- 額(おでこ):体温調節のために汗をかきやすい
- 頭皮:毛穴が多く、蒸れやすいため汗をかきやすい
- 脇(わきの下):アポクリン汗腺が多く、においの原因になることもあり
- 首:血流が多く、体温調節のために発汗しやすい
- 背中:特に肩甲骨周りは汗腺が多く、蒸れやすい
- 胸(胸元):緊張やストレスで発汗しやすい
- 手のひら:交感神経の影響を受けやすく、緊張や興奮時に汗をかきやすい
- 足の裏:汗腺が多く、蒸れやすいため汗をかきやすい
- 股(鼠径部):下着や衣類で蒸れやすく、汗がこもりやすい
- 膝の裏:皮膚が重なりやすく、汗がたまりやすい
また、おむつを着用している場合には、1日1回の陰部洗浄(ぬるま湯で洗い流すだけでも効果があるといわれています)をすることで、感染症予防になります。
基礎疾患がある子の場合、感染症から急激に全身の状態が悪化する可能性が高いので、うちでは1日1回の陰部洗浄のケアだけはどんな時も欠かさず行うようにしています。
4.清拭に必要なもの
清拭に必要なものとしては以下があげられます。
- ぬるま湯(適温:40℃前後)
- 石鹸、ボディソープ類
- 防水シート(ベッドが濡れないように)
- バスタオル、フェイスタオル
- 清潔な洗浄用タオル、ガーゼハンカチ
- ビニール手袋(必要に応じて)
- 保湿剤やスキンケア用品
- 洗面器
- シャワー代わりのドレッシングボトル(細かい穴があいているタイプが使いやすい)など
5.清拭の準備
清拭をはじめるときは、以下のような準備をしましょう。
①室温調整
清拭を行う前に、まず室内の温度を適温に保つ(22~25℃)ことが必要です。
②お子さんへの声かけ
その後、準備物を手元に用意し、「体を綺麗にするよ」などの声かけをします。
③体温が低下しないようにタオルをかける
清拭中は、拭いていない部位をタオルや毛布で覆い、体温低下を防ぐように注意します。
④蒸しタオルの用意
体を冷やさず温めてあげるためにも、体を拭くタオルは蒸しタオルを用意するのがおすすめです。


蒸しタオルを作る時には、以下の方法が簡単です。ぜひ試してみてくださいね。
1.フェイスタオルを水でぬらし、やや堅めに絞る。
フェイスタオルは、ある程度厚みがあるほうが温かさをキープできます。
2.タオルを電子レンジ(600W)で、約1分間、加熱する。
タオルを耐熱皿の上にのせる、もしくはラップで包んでから加熱すると衛生的です。
3.タオルをレンジから取り出し、パンパンと上下に振りながら広げて、ちょうどいい温度まで冷ます。
(火傷に注意するぐらいの熱い温度から、すぐに人肌以下の温度に冷めるので、冷ますタイミングが大事)
6.清拭の手順
清拭をはじめるときは、以下の手順で行うことをおすすめします。
①タオルをお湯に浸して絞り、温かい状態にする
寒い時期だとタオルがすぐに冷めてしまうので、レンチン蒸しタオルを2個ぐらい作ることをおすすめします。
②体の清潔な部分から拭き始め、汚れやすい部分を最後に拭く
タオルをキレイに保つために、体を拭く順序は以下のようにするのがおすすめです。
①顔や手などの汚れが少ない部位
⇓
②脇・足・陰部などの汚れやすい部位
③拭いた後は、乾いたタオルで水分をよく拭き取る
拭き終わったら、水分をしっかり拭き取ってあげましょう。
④保湿剤をしっかりと塗り込む
乾燥を防ぐため、ベビーオイルや保湿クリームなどの保湿剤を塗ることをおすすめします。
7.拭き方のポイント
頭から足に向かって、皮膚を傷つけないように優しく拭くことが重要なポイントです。
頭(上半身)から拭く理由として、主に以下の3つの点が挙げられます。
①清潔な部位から汚れやすい部位へ拭く
清潔な部分から拭くことで、汚れを広げるリスクを減らす意味があります。
顔や上半身は比較的清潔であるのに対し、下半身(特に足や陰部)は汗や汚れがたまりやすい部位です。
陰部や足を拭いた後に同じタオルで顔を拭くと、感染リスクが高まるため順序が重要となります。
②血流の流れに沿うため(循環促進)
上半身から拭く理由は、循環を促進する意味もあります。
血液は心臓から全身へ流れ、静脈を通って心臓に戻るようになっています。
そのため、頭から拭くことで、血行を促進しつつ、なおかつ心地よい刺激を与えられます。
特に、マッサージ効果を考慮すると「心臓から遠い部位(末梢)へ向かって拭く」のがベストといえます。
③体温低下を防ぐため
頭部や顔を先に拭き、すぐに乾かすことで体温低下を防ぐ意味があります。
そして、下半身を拭くことを最後にすることで、冷えやすい足を拭く際にタオルや毛布で他の部位を覆い、寒さを感じにくくする効果もあります。
8.各部位の清拭方法
部位別の拭き方は、以下の通りです。
顔
目→鼻→口→頬→額の順に軽く拭く。
胸と腹部
心臓に負担をかけないように、優しく拭く。
背中
体位を少しずつ変えながら、広範囲をしっかりと拭く。
腕と脚
手先や足先(指の間も意識して)丁寧に拭き、関節部も忘れずに拭く。
陰部
最後に清潔なタオルを使い、お湯で洗い流した後優しく拭く。
9.清拭に使える時短&便利グッズ


さて、ここからは、娘の入院中に教えてもらった我が家のやり方をお伝えいたします。
基本的に母1人で清拭を行っているため、ワンオペでもできる「素早く、簡単に」を最優先に考えています。
主にリハビリ病院で教えてもらったベッド上での体拭きの方法を中心としてご紹介します。
また、介護福祉士さんのケアの方法も取り入れています。
使用している物品について
使用している物品については、衛生面を考えた上で使い捨てをしやすく、比較的安価で、どこででも手に入りやすいものを中心としています。
そのため、イオンのペットシートや西松屋の防水シートなども使っています。
ただ、直接体に触れるものなので、各ご家庭に合わせてこだわりがあると思いますので、1つの方法として「こんな使い方もあるんだなぁ」と気楽に見てもらえたらうれしいです。
アイス流の清拭のやり方
①部屋の温度を整える
半袖でちょうど良いぐらいに暖かくする(清拭前に、デロンギ、加湿器、暖房をフル稼働して部屋を温める)
②清拭に使う物品を準備する
わが家では、以下のグッズを用いて清拭を行なっています。
- レンチン蒸しタオル、もしくは、温めても使える からだふきタオル 超大判
- 42℃ぐらいのやや熱めのお湯を入れたマヨネーズボトル(100均で購入)
- タオル、バスタオル、ガーゼハンカチ
- 保湿剤
- 防水シート(赤ちゃんグッズの大きめサイズ)とペットシート(なるべく大きめサイズ)
- 皮膚清拭・洗浄フォーム(水を使わない洗浄剤、個人的にリモイスクレンズ好き)
- 水のいらないシャンプー
- パジャマ
- 気管切開のケア用品(カニューレバンド、Yガーゼなど)
- ベビーオイル
- 綿棒(細かい部分のケアに使う時もあり)
- おしりふき、清浄綿
- ビニール袋(ペットシートなどを捨てるため)
- 着替えのパジャマ
③防水対策をした上で、清拭を行う
体が冷えないように短時間で行うことと、お湯で流すのは最低限にすることを意識しています。
やや熱めのお湯を用意するのは、清拭中に徐々にお湯が冷めることを踏まえた上での温度設定です。
ボディーソープは、お湯で洗い流す必要があるため、手間を省きたいうちでは使いません。
代わりに、水のいらないシャンプーや拭き取りケアができる洗浄剤を活用しています。
手順は、以下の通りです。
頭→上半身→おしり→下半身→顔・気管切開部の順に洗い、保湿剤を塗る。
〈個人的なポイント〉
- 頭を洗う時とお尻を洗う時は、フラットタイプのおむつを使うか、高齢者用のおむつを開いたものを頭の下に敷く
(高齢者用は、吸水量が子ども用より断トツに多いらしい)
頭皮の清拭は、基本的には、ドライシャンプーがほとんど。
- 汗をかきやすい部位は、洗浄剤をつけて拭き取るだけ
(夏ならお湯で流すこともあり)
- お湯で流すのは、お尻・手先・足先のみ
お尻は、洗浄剤をつけた後お湯をかけて洗う。洗う前に、ベビーオイルをつけたおしりふきで拭くと、便などの汚れがスルッと綺麗に落ちやすい。
手先と足先は、温めると体がゆるむ効果も狙っています。
- 顔と首元(気管切開部)のケアは、最後に
洗浄剤をつけて、清浄綿、レンチン蒸しタオルやガーゼハンカチで拭き取ります。
蒸しタオルで、顔を拭いた後、耳の後ろをゆっくりと優しく拭くのもおすすめです。
イメージとしては、美容院で髪を洗った後に、美容師さんが耳の中を軽く水を拭った後に耳の後ろを温めるように、耳全体を包むようにする動きです。
耳のケアの最中、娘はとても気持ちが良さそうに微笑みます。
10.おわりに
通常、訪問看護や居宅介護で依頼しているケアでも、感染症の拡大や天候などにより、急遽家族だけで対応することになる場合もあるかと思います。そんな時のためにも、清拭のやり方を覚えておくと安心ですよね。
ケアの方法について、他の選択肢を知っているだけでも、少し気持ちが楽になるのではないでしょうか?
なお、清潔を保つケアは、必ずしも毎日同じやり方でなくても大丈夫です。ご家庭でやりやすい方法を見つけてみてください。
私も、今回改めてリサーチした結果、清拭の具体的な方法や手順の意味を知ることができました。今後はよりスムーズな清拭を娘に行うことができるような気がします。
お風呂に入れない日が続いても、ポイントを抑えたケアを適切に行うことで清潔を保つことで、皮膚トラブルなどを防ぐことができます。
在宅でケアが必要なお子さんがいらっしゃる家族の方は、ぜひ、絵本屋だっこの体験談を参考にしてみてくださいね。
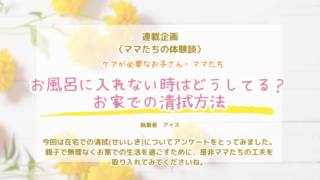
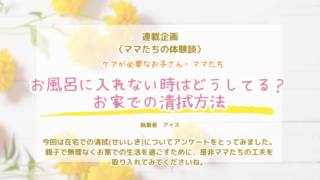
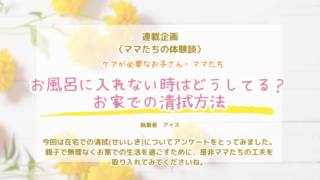



乳幼児から成人した後の清拭の便利グッズについても、ママたちが回答してくれています。ぜひこちらも参考にしてみてください。
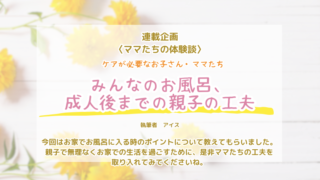
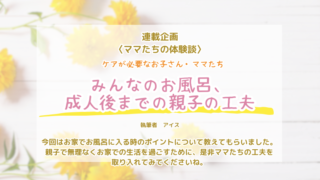
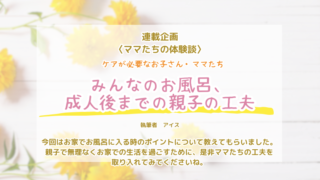
特に、寒い時期のケアは親も負担が増えますので、親子ともに快適に過ごせる環境作りを心がけてくださいね♪
サポートスタッフ・相談室ピアサポーター アイス
ひとりで悩んでしまう方は『絵本屋だっこ相談室』へご相談ください


絵本屋だっこでは、障害児ママたちが安心して相談できる場所をつくるため、また、障害児がいて外で働けないママたちの居場所をつくるため、『絵本屋だっこ相談室』を開設しました♪
ぜひお気軽に、ご相談にきてくださいね。
新米ママたちへ向けたお役立ち情報の掲載
こちらのコラムページでは、重心児や自閉症・発達障害などの障害児を育てる先輩ママたちにご協力いただき、新米ママたちへ向けたお役立ち情報を発信していきます!
<コラムに載せる内容例>
- 障害児ママたちの体験談まとめ【連載企画】
- 障害児向けの便利グッズ
- 障害児育児のお役立ち情報
- 障害児が使える福祉サービスについて
- 障害児の将来に関すること など……
今、子どもに障害を宣告され、不安いっぱいのママたち、まだまだ子どもが小さく先が見えず不安なママたちへ、必要な情報を届けられればと思っています。
コラム掲載のご案内は、公式LINEやインスタなどで行なっていきますので、ぜひチェックしにきてくださいね!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
▼絵本屋だっこInstagram


コラム記事を書いてみたい方を募集中!
絵本屋だっこでは、子どもに障害があって外に働きに出られないママたちの働き場所をつくる取り組みをスタートさせました。こちらのコラム記事執筆も、そのひとつです。
報酬は多くは出せませんが、お手伝いいただける方がいればぜひ公式LINEよりお問い合わせください。一緒に活躍の場をつくっていきましょう!
▼公式LINEのご登録・お問い合わせはこちら
ボランティアさんも募集中♪
絵本屋だっこコラムでは、障害児ママ以外にも、情報発信をしてくださる方を募集します♪
たとえば、特別支援学校の先生、リハビリの先生、デイのスタッフさんなど、障害児ママたちの不安を解消できるような情報発信をしたいという方がいましたら、ぜひご協力ください!
みなさまのあたたかなご協力をお待ちしております(^^♪